�����(����)-��17��
�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������
��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���
�������Ĥǥ�������ͬ�����ʡ�
�����ˤ��ؤÚݟo���Ԥ��ȡ������Ĥ˥���������ζ������͡���Ц�����ɤ����ơ�����ʤˑB�Ȥ����ä��Τ����ˤ�����Ǥ��ʤ��ä����i�����ۤɡ��Ɇ����Ф��Ƥ��ޤ����^���ФǤ�ޤ��뤷���ʤ뤰�餤�����z��Ǥ��ޤ����Y�֤ΤȤ������֤��餺�˿�����Τ���Ƥ��ޤ��Τ����顢������鿼���ʤ����������˼���Τˡ�����˼����˼���ۤɡ��^���ФǤϤ��äȿ����A���Ƥ��ޤ��Τ��ä���
�������������뤱�ɡ����ˤϳ��������趨�Ȥ�����Σ���
���ʤ���
�����ˤ��Ϥä���𤨤�Ți���@�����褦��Ŀ��Ҋ�_�����o���Σ������ȴ�������������i�Τ褦�����_���त�櫓�Ǥ�ʤ����l����ߣ�����ꤹ��Τ��浹��������Ϣ������˚i��Ҋ��ȡ��i������Фǥ��ש����뤰��Ȥ����줼�ơ��������ä������ȅۤ�����
�������Ԥ��С������ޤ���ФäƤ������ä����Ƥ�������ɡ���������
���ä��ˤ���С�
���ޤ�����ؚݤʤ��𤨡����ˤϥ��쩡���ڤ��Ф����롣ʳ�٤Ƥ����g�ϻ�Ԓ�ʤ��Ɯg���������˼���������˥��ש�����ڤؤ�ߤ֡�������B��Ƥ��褦�����ޤ���������Ϛi�΄��֤����������������ˤ��˳Фʤ��ȡ��ʤ��Ƥ�����������Ǥ⡢�������Ƥ��ޤ����ȤǺΤ������줽���Dz����ä��������Ԥäơ�����ʤȤ��Ԥ����ˡ����ˤϥ����ޤ˿��ޤ�롣����״�r����Ƥ������Τ�������Ȥ�@�A���������Τ����Է֤Κݳ֤��������֤���ʤ��ä���
�����㤡�����դ��餪���Ǥä��ԤäȤ����֡�����Ȥ��ä����������Ǥ����˼�������͡�äƤ�ȘS���������ۤ顢���ˤ�ͬ���ش��������
���e���ش���ͬʿ������ä��������Ǥ���櫓�Ǥ�ʤ�������
���������⤷��ʤ����ɤ����ۤ�ȡ�����ū�ʤ���äơ�
�����h����i���Ŀ��Ҋ�ơ����ˤϤ������ϡ��Τ��Ԥ�ʤ��ä����������Ǥ��뤫�ɤ����ʤ�ơ��F�r��ǤϷ֤���ʤ����Ȥ��������顢�i���٤��������ԤäƤ⽡�ˤȳ����뤫�ɤ����ϡ��ޤ�������������ˡ��ش���ͬʿ��������Ԥä�����������褦�ʤ�ΤǤ�ʤ����������ϡ��i��Ԓ�����Ƥ����ʤ��ʤꡢ���ˤ������Ϥ��ä���
�������������ޡ�
�������Ϥ�ã���������������ҹ�ޤǤˤώ��äƤ��뤫�顢Ϧ����äƤ����Ƥ衹
���������~�˽��ˤ΄Ӥ���ֹ�ޤä���Ϧʳ�����äƤ����Ƥ�����m�ޤ�Ƥ⡢���i����ФϤ��Ǥ˿դǡ��Τ�������ʤ��I����ؤ����ʤ���Ф����ʤ����������С���س������ʤ����ˤ��٤������Ӥ��������
�����դ��⤸�㤬���ä�������ϥ��쩡����ä����顢���A��ʳ�٤����ʩ����
�������Ϥ�����
���ꥯ�����Ȥ��줿��Τ��ȤƤ��浹�ʤ�Τ��ä����ᡢ���ˤϤĤ����Ӥ����������Ϥ��Ƥ��ޤä�������Ǥ�i�Ϥᤲ���ˡ����A���ä��顢���फ�ʤ��������Ǥ�ԩ���ޥ��Ӥ�������ʤ����ȶ����ԤΤ褦�˅ۤ��ơ�����Ȑ���Ǥ��������äƤ����Ƥ��m�ޤ졢������ꥯ�����Ȥ��Ƥ����Τ�����ȤȤ��ƤϤȤƤ��Ҥ������Ȥ������ʤ�������äƴ��äƤ��뤳�Ȥ����D�ߤ������Ӥ��ʤ�˼�ä���
�����Ŷ����������ʣ���
�����ש������ˤ�ͻ�������ƴ������Ԥ��i�ˡ����ˤϤ���Ϣ������˴𤨤���
�������֤��ä��衹
���ɤ�ʤ��Ӥ�����Ƥ��Ƥ⡢�i��ЦǤ����Ԥ��Τǽ��ˤ��˷��ʤ��˳Ф����������뤳�Ȥ��Ӥ��ǤϤʤ������������ơ�ʳ�٤�����Τ��ԤäƤ���뷽�������κ��g��������Է֤��Ԥ������롣�����Ǥʤ��ȡ��Τ⤫�⤬���֤������ʤ��ݤ�������
�����Ĥ��g�ˤ����Ӥ����Ԥ�����Ϥɤ����������Ƥ��ޤä���
�����δ�������ޤ줿�Τϡ��Ɇ����ä����i���Է֤Τ��Ȥ��Ӥ��ʤϤ��ʤΤˡ��ɤ�����Ц�Ԓ�������Ƥ��뤳�Ȥ������������������ޤ����Ӥ������Ԥä�Ҋ�Ť��Ȥ�������Τ������������������Ƥ��ޤ��ȡ��������¤�������Ф��Τ�Ф��롣�֤ΤҤ�ϡ��ޤ������g���䤿���ʤ롣
�����㡢�����������Ƥ��뤫�顣�������ʩ����7�r��8�r�ˤώ��äƤ�����˼�����W���ʤ�褦���ä��顢�B�j���뤫�项
�������e�ˤ��ʤ��Ƥ�����
���ۤ��褦���Ԥ��ȡ��i��Ц�äơ����뤫�项���Ԥäƥ�ӥ�������Фä��������ʤꃞ��������Ƥ⡢�Τ��Y������ΤǤϤʤ������ɤäƤ��ޤäơ��i�Τ��Ȥ��Ť�����ʤ��ä������ä��Τϡ�ͣ늤��𤭤����դ��顣�i����äƤ��뤱��ɡ��������������ĤĤ��ä���ǰ�ʤ�С�Ҫ��ʤ����Ԥ���н~��������ʤ��ä����������ɤ�ۤ��m�ޤ�Ƥ�Ҫ��ʤ����Ԥä����������Ԥäơ�һ���I�Ϥ��Ƥ����Ϥ���������ʤΤˡ��ꥯ������ͨ�ꤴ����äƤ���Τ��Ť����ʤ��ä���
�����������ɤ��ʤäƤ����衹
���������¤������Ƥ⡢�𤨤ʤ�Ҋ�Ĥ���ʤ��ä�������ˡ�Ҋ�Ĥ���ݤ⤢�ޤ�o���ä��������Τ��Ȥ�֪��Τ����٤������ä���
��7�r��8�r���餤�ˤʤä��鎢�äƤ�����ԤäƤ����i���ä�������������9�r�ˤʤ����Ȥ��Ƥ���Τ˼Ҥˤώ��äƤ��ʤ��ä���ѧУ���ФäƤ���r���顢�Y���W���ʤ뤳�Ȥ⤿�Ӥ��Ӥ��ꡢĸ��һ��ŭ�äƤ���Τ�Ŀ�ˤ������Ȥ����ä����B�j��1�����餤���Ƥͤ��Ԥä�ĸ�ˌ����ơ��i��Цǡ��֤��ä������Ԥä������W���ʤ�Ȥ��B�j�����뤳�Ȥϟo���ä�����ԏ���ڤ����ʤΤ����Ԥ������ơ����ˤϥƥ�Ӥ��Դ����줿��
���ե饤�ѥ���Фˤϡ����Ŷ�������äƤ��뤷�����i����Фˤϴ��ꥵ������ä��Ƥ��롣���A������פ����äƤ��äơ����ȤϚi�����äƤ��������״�B�ˤʤäƤ��롣һ�ˤ�ʳ�٤褦����˼�ä�����Ƭ�Ť���ΤϽ��ˤʤΤǡ����äƤ���ޤǴ��Ĥ��Ȥ�Q������줫�顢���Ǥ�2�r�g�ϽU�äƤ��롣���äƤ��ʤ��ʤȡ����v�ؾA�����Ҋ�Ĥ�Ƥϡ��ιʡ��������äƤ��������Է֤�Չ�ᡢ�虜�Ȥ餷���ƥ�Ӥ�Ŀ��������
����ʳ�Խ����Τ�ڤˤ��Ƥ��ʤ����������Ȥۤɤ��餰�뤰��ȸ����Q�äƤ��롣���ä���ʳ�٤Ƥ��ޤä����������ΤǤϤ�˼���������Ӥ����Τ��浹�ˤʤ�ե������ƾ�줫���äƤ��������դϤ��ޤ��ߤ줺���礯Ŀ��ҙ��Ƥ��ޤä���������������礤�r�g�����ߚݤ��u�äƤ��Ƥ������ƥ�Ӥϴ���פ��Τ��äƤ��ʤ������Ȥ��ȤȲ����ؤ����ʤäƤ��ơ��^����ä�Ŀ��ҙ�ޤ����Ȥ��뤬���ߚݤη����٤äƤ��뤻�����ɥ�ɥ��ҕ�礬�����ʤäƤ�����
���ݸ������r�ˤϡ��ߤäƤ��ޤäƤ�����
���Ҥ�ǰ��Я�����_���Ƥ��顢�s���Εr�g��������^���Ƥ��뤳�Ȥ˚ݸ����������äȡ����ˤΤ��Ȥ����顢�Ԥä��r�g�ˎ��äƤ��ʤ��Ƥ⡢֪���Ƥ���褦�ʚݤ����ƚi�Ϥ��ä�����_������
������������s�����ؤꤿ���ä���������Ƥ����鎢�뤳�Ȥ�����Ɖ��ФˤʤäƤ��ޤä�����ӥ�늚ݤ������Ƥ���Τ�Ҋ�ơ��i�Ͼ����˼Ҥؤ���롣���������Ƥʤ������̤�������¤�i������ӥ�����_����ȥ��ե�����ǽ��ˤ��ƥ�Ӥ�Ҋ�Ƥ�����
����������
���������ޤ��Ԥ����Ȥ������i�ϱ������֤��������֤ǿڤ�Ѻ�����ơ��礬���¤˄Ӥ��Ƥ��뽡�ˤˤ��äȽ��Ť����Ϥ���Җ���z��褦�˽��ˤ��Ҋ��ȡ�����飧�����Ƥ��ơ����䤹�����Ϣ�����ƤƤ������������������Ƥߤ�ȡ����ˤϳ��礯����ϴ媤ʤɤƤ����褦�ʚݤ����롣����˼Ҥ��ФΒ߳����äơ���ǰ�Ф����äƤ���������ƣ�줬���ޤäƤ��ޤä��Τ�������˼�����𤳤��ʤ��褦���ä��x�줿��
��ˮ��⤦��˼�äơ����i����_���롣���i����жΤ��ä��줿���ꥵ�����Ŀ����ꡢ���A�����äƤ�����m������Ȥ�˼������������귵�äƥ������Ҋ��ȡ��ե饤�ѥ���Фˤϥꥯ������ͨ�����Ŷ����������Ƥ��롣ʳ�٤����E��o�����ݤĤ���ä���Ƥ������Ŷ�����Ҋ�Ĥ�Ƥ��顢���ե�������ޤƤ��뽡�ˤ�Ŀ������
�������⤷�����ơ����äƤƤ��줿�Σ���
�������ڤ˳����Ƥߤ������Ť����ʤ��ä����i�Τ��Ȥ��ӤäƤ��ơ�Ҋ�Ƥ���������������Ԥä�Ŀ�Ƥ������ˤ������äƤ���Τ���äƤ��Ƥ����櫓���ʤ������������Ԓ����������Ԓ���褦�ˤʤäƤ��줿���Ȥ��äơ��٤���Ц�����ʤ�˼�äƤ����Τ���������Է֤�һ�w�ǡ��i�ϥ��ꥬ����^��������롣
�����դ��顢��Ц�������ȤϷ֤��äƤ�����ͣ늤�����ð��ˤʤä��Ҥ��ФǶפäƤ������ˤ�Ҋ�Ƥ��顢���ˤΤ��Ȥ��ŤäƤ����ʤ��ʤä����Ҥ��Ф˾Ӥ뤳�Ȥ������������ˤ����x���Τ��٤��������Τ��Ƥ���Τ��֤���ʤ��ä���������п�����ۤɡ�˼�������Ҥ��뤫�顢˼�ä�ͨ����ЄӤ��Ƥߤ�������ȡ����ˤΑB�Ȥ���äƤ����Τǡ����य�@������
��Ԓ�������Ƥ�oҕ������˼�äƤ����Τˡ����ˤ����줿���ȤϤ����ȴ𤨤Ƥ���롣���줬�Ҥ����⤢�ꡢ�ष���ä���
�����ˤ����Τ��Ƥ���Τ��֤���ʤ���
�����i������飧��ơ��i�ϥ��ե�������ޤƤ��뽡�ˤ������ä������������äƤ��Ƥ⡢��˯���Ƥ��ޤäƤ���Τ������ˤ�Ŀ��ҙ�ޤ�����ϟo�������⤿����ƾ��ơ�����������Ф��Ƥ����ˤϡ����ޤƤ���褦�ˤ�Ҋ������
���������ˡ�
���i�ϼ��e���äơ����ˤ��𤳤��������ä����Ŀ���_�������൱�ߤ����Τ������ˤϤޤ�Ŀ��飧���롣����ʤȤ������ޤƤ��Ƥ��Lа��Ҥ��Ƥ��ޤ���������������驡����L�ϡ����ˤ���ֱ�Ӵ��������Ƥ�����
���𤭤ơ��Lа�Ҥ���
����ȤϏ���˓e���äƤߤ�����Ŀ���_���똔�Ӥ�ʤ��ä�����˯���Ƥ��뽡�ˤ�Ҋ��Τϳ���Ƥǡ��ޤƤ����ˤϤ��Ĥ��ꤢ�ɤ��ʤ��ä���ˤ����ä������ë��ָ�Ǥɤ��ơ��i�Ͻ��ˤ��~��ָ�Ǔ�Ǥ롣ü�g���������Ƥ��뤻���������Ĥ�ü�g�˰����ĤäƤ��롣�����ĤäƤ���ü�g��ָ�Ǔ�ǡ��i���������
��ħ��������ȤǤ��Ԥ��Τ������������ȴ���������ǰ�ǡ��i���Է֤��ΤƤ���Τ��ݸ������Ӥ���ֹ���
�������á�
��©���褦����������ơ��i��һ�ݤ��Է֤�������������Τ�֪��ʤ����ˤ������餺���g�䤫�ʱ�����ޤƤ��롣�Ӥ����ä������Ӥ�����˼�äƤ�����һ�塢�Τ��Ӥ��ǺΤ��ä��ʤΤ��֤���ʤ��ʤäƤ��ޤä���
�������Τ��褦�Ȥ��Ƥ���������ϡ�
������褦�Ȥ�������ָ���@�魯�ȡ�ȼ���Ƥ���褦�˟ᤫ�ä���������ָ���x���ơ��i�Ͻ��ˤ˱�������һ�̤��礯����ӥ���Ӥʤ��ʤ�ʤ��ȡ���ȤϤ����n�Ӥ�ֹ���ʤ��褦�ʚݤ�������
���ˤϺ�����Ŀ��ҙ�ޤ����������÷Ť��Υƥ�Ӥ�ɰ���ˤʤäƤ��ơ������������ȟ�����������ͻ�������ͤ��K��äƤ��ޤäƤ�����Ԥ����Ȥ���ҹ�ʤΤ�������˼�����ڤˤ����äƤ���rӋ��Ŀ����ȡ���ǰ3�r��ؤ����Ȥ��Ƥ���������ʕr�g�ˤʤäƤ⡢�ޤ��i�ώ��äƤ��Ƥ��ʤ��Τ��Ƚ��ˤ����v�ؤ��Ф������äƤ��Ƥ��뤫�ɤ�����_�J������
�����v�ˤϽ��ˤ�ѥ�ȡ��i��ѥ��ܞ���äƤ��롣ѥ��������Ԥ����Ȥώ��äƤ��Ƥ���Τ����������ˤϥ�ӥؤȑ��롣���äƤ��Ƥ���ʤ鎢�äƤ��Ƥ����һ�Ԥ��餤�����Ƥ���Ƥ�褫�ä��Τˤȡ����ˤ��쾮��Ҋ�Ϥ��롣����Ǥ⤽���ľ���Ԥ��ʤ��Τϡ����äƤ����˼����Τ���������������ӥˑ��ꡢ���å�����Ф��Ƚ��ˤ����ä��ޤޤ�״�B�ǺΤ⤫�⤬�ФäƤ�����
�����äƤ��ơ����ʳ�٤Ƥ��ʤ�������������ޤ�ǰ���V���Ƥ����ո����֤귵���Ƥ��ơ����ˤϥե饤�ѥ�˻�������i��ʳ�٤ʤ��ä��Ȥ��Ƥ⡢����ǰ���餤���ä���һ�ˤ�ʳ��

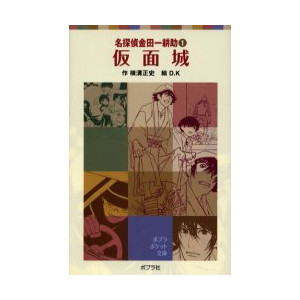

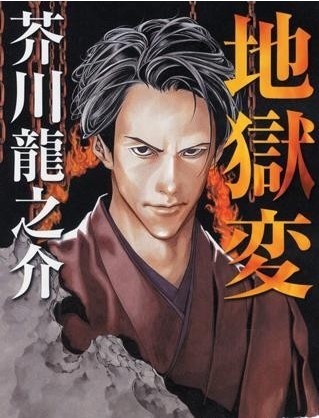
![(����ͬ��)[����]�ҵĸ�����ܹ�����](http://www.cijige2.com/cover/56/56585.jpg)
![(�վ�ͬ��)[Legal high����]ϴ�Է���](http://www.cijige2.com/cover/95/95502.gif)