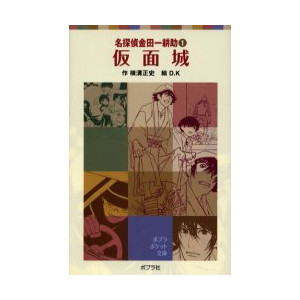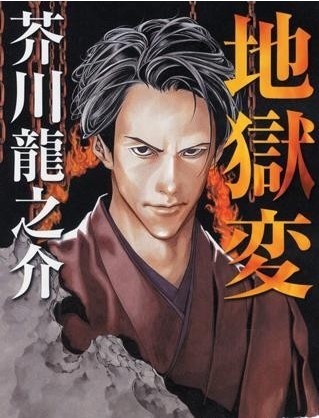¹ΔΟφ≥«(»’ΈΡΑφ)-ΒΎ7’¬
Α¥Φϋ≈Χ…œΖΫœρΦϋ Γϊ Μρ Γζ Ω…ΩλΥΌ…œœ¬Ζ≠“≥Θ§Α¥Φϋ≈Χ…œΒΡ Enter ΦϋΩ…ΜΊΒΫ±Ψ ιΡΩ¬Φ“≥Θ§Α¥Φϋ≈Χ…œΖΫœρΦϋ Γϋ Ω…ΜΊΒΫ±Ψ“≥ΕΞ≤ΩΘΓ
ΓΣΓΣΓΣΓΣΈ¥‘ΡΕΝΆξΘΩΦ”»κ ι«©“―±ψœ¬¥ΈΦΧ–χ‘ΡΕΝΘΓ
ΓΗœ»…ζΓΔΛΙΛΏΛόΛΜΛσΓΘΛΫΛΠΛ«ΛΖΛΩΓΘΤϋΛΛΛΤΛΛΛκΛ–ΛΔΛΛΛΗΛψΛΔΛξΛόΛΜΛσΛ«ΛΖΛΩΓΘΛήΛ·ΓΔëιΛΛΛόΛΙΓΘΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛΈΛΩΛαΛΥëιΛΛΛόΛΙΓΙ
ΓΗΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛήΓΔΛήΛ·Λβ ÷¹ΜΛΛΛόΛΙΓΘΛήΛ·ΛβΛΛΛΟΛΖΛγΛΥΓΔψy¹ΔΟφΛ»ëιΛΛΛόΛΙΓΙ
ΓΓ»ΐΧΪΛβΛΫΛ–ΛΪΛιΛ≥Λ»Λ–ΛρΛΫΛ®ΛκΓΘΛΔΛλΛΪΛιιgΛβΛ Λ·ΛΠΛΝΛΊΛœΛΛΛΟΛΩ»ΐ»ΥΛœΓΔΛ≥ΛΠΛΖΛΤΛΩΛ§ΛΛΛΥΛœΛ≤ΛόΛΖΚœΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΗΛηΛΖΓΔΛΫΛλΛΗΛψ»ΐ»ΥΝΠΛρΚœΛοΛΜΛΤΓΔψy¹ΔΟφΛ»ëιΛΠΛΈΛάΓΘ ≥ΛΠΛΪ ≥ΛοΛλΛκΛΪΓΔΈΡ―εΛ·ΛσΓΔ»ΐΧΪΓΔΛ…ΛσΛ Λ≥Λ»Λ§ΛΔΛΟΛΤΛβΓΔΆΨ÷–Λ«»θ“τΛρΛœΛΛΛΝΛψΛΛΛΪΛσΛΦΓΙ
ΓΓΈΡ―εΛ»»ΐΧΪΛœèäΛ·ΓΔèäΛ·ΛΠΛ ΛΚΛΛΛΩΓΘΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛœΛΥΛΟΛ≥Λξ–ΠΛΟΛΤΓΔ
ΓΗΛηΛΖΓΔΛΫΛλΛ«‘£ΛœΛ≠ΛόΛΟΛΩΓΘΛΒΛΤΓΔÜ•νΘΐΛœΫπΛΈœδΛάΛ§ΓΔΈΡ―εΛ·ΛσΓΔΛ≥ΛΠΛ ΛΟΛΩΛιΓΔΛ ΛΥΛβΛΪΛβΛΠΛΝΛΔΛ±ΛΤΛ·ΛλΛκΛάΛμΛΠΓΙ
ΓΓΈΡ―εΛœœψ¥ζΉ”Λ»ΛΈΛΔΛΛΛάΛΥΛ»ΛξΛΪΛοΛΖΛΩΓΔ»ΐΛΡΛΈΦs χΛρΥΦΛΛΛάΛΖΛΩΓΘΛΖΛΪΛΖΓΔΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛΥΛœΛΪΛ®ΛιΛλΛ ΛΛ®D®DΓΘΛΫΛ≥Λ«ΛΛΛΝΛ÷ΛΖΛΗΛεΛΠΛΈ‘£ΛρΛΙΛκΛ»ΓΔœδΛΈΛΔΛ±ΛΪΛΩΛόΛ«ΛΠΛΝΛΔΛ±ΛΩΓΘ
ΓΗΛ ΛκΛέΛ…ΓΔΘΗΘ°Θ±Θ°Θ≥ΛάΛΆΓΘΛηΛΖΓΔΛΔΛ±ΛΤ“äΛΩΛόΛ®ΓΙ
ΓΓΘΗΓ≠Γ≠Θ±Γ≠Γ≠Θ≥Γ≠Γ≠ΓΘ
ΓΓΞάΞΛΞδΞκΛρΛόΛοΛΙΛ¥Λ»ΛΥΞΝ©Γ°ΞσΓΔΞΝ©Γ°ΞσΛ»ΓΔΛΙΛΚΛΖΛΛ“τΛ§ΛΖΛΩΓΘΛΫΛΖΛΤΓΔΛΒΛΛΛ¥ΛΈΘ≥ΛΥΚœΛοΛΜΛΩΛ»ΛΩΛσΓΔΞ―ΞΝΞσΛ»ΛΪΛΙΛΪΛ “τΛ§ΛΖΛΤΓΔΫπΛΈΛ’ΛΩΛ§ΛΔΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΛ ΛΪΛΥΛœΑΉΛΛΛόΘέΘΘΓΗΛόΓΙΛΥΑχΒψΘίΘϋΨdΓΕΛοΛΩΓΖΛ§Ξ°ΞΟΞΝΞξΛ»ΓΔΛΙΛ≠ΛόΛ Λ·ΛΡΛαΛ≥ΛσΛ«ΛΔΛκΓΘΈΡ―εΛœΛ’ΛκΛ®Λκ÷ΗΛ«ΓΔΛΫΛΈΛόΘέΘΘΓΗΛόΓΙΛΥΑχΒψΘίΨdΛρΛ»ΛξΛΈΛΨΛΛΛΤΛΛΛΟΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΛΠΛΝΛΥΓΔΞΔΞΟΛ»ΛΛΛΠΫ–Λ”…υΛ§ΓΔ»ΐ»ΥΛΈΛ·ΛΝΛ”ΛκΛΪΛιΛΛΛΟΛΜΛΛΛΥΛ»ΛσΛ«≥ωΛΩΓΘ
ΓΓΛΔΛΔΓΔΛ ΛσΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛάΛμΛΠΓΘΛόΘέΘΘΓΗΛόΓΙΛΥΑχΒψΘίΨdΛΈΛ ΛΪΛΥΛœΘϋυçΓΕΛ±ΛΛΓΖΘϋ¬―ΓΕΛιΛσΓΖΛ·ΛιΛΛΛΈΞάΞΛΞδΛ§Νυ²ÄΓΔΛΒΛσΛΕΛσΛ»ΛΖΛΤΛΪΛ§ΛδΛΛΛΤΛΛΛκΛ«ΛœΛ ΛΛΛΪΓΘΛΔΛΔΓΔΛΫΛΈΛΏΛ¥Λ»ΛΒΓΔΛΙΛ–ΛιΛΖΛΒΓΔ≥ύΛΥΓΔ«ύΛΥΓΔΉœΛΥΓΔΛΪΛ§ΛδΛ≠ΛοΛΩΛκΛόΛ®ΛΥΛœΓΔΜΤΫπΛΈœδΛΒΛ®ΛΏΛΙΛήΛιΛΖΛΛΛέΛ…Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΗΛΔΛΔΓΔΞάΞΛΞδΛάΓΘΞάΞΛΞδΛάΓΘΞάΞΛΞδΞβΞσΞ…ΛάΓΘΛΖΛΪΛβΓΔΛ≥ΛλΛάΛ±ΛΈ¥σΛ≠ΛΒΛΈΛβΛΈΛ§ΓΔ άΫγΛΥΛΛΛ·ΛΡΛβΛΔΛκΛœΛΚΛ§Λ ΛΛΓΘΛΫΛλΛ§Λ…ΛΠΛΖΛΤΛ≥ΛΈœδΛΥΓ≠Γ≠ΓΙ
ΓΓΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛœΓΔöίΛ§Λ·ΛκΛΟΛΩΛηΛΠΛ ΡΩΛΡΛ≠ΛρΛΖΛΤΓΔœδΛΈΛ ΛΪΛρΛΥΛιΛσΛ«ΛΛΛκΓΘ
ΓΗΛΜΓΔœ»…ζΓΔΛ≥ΓΔΛ≥ΛλΛœ±ΨΈοΛ«ΛΖΛγΛΠΛΪΘΩΓΙ
ΓΗ±ΨΈοΛάΛ»ΛβΓΘΛΥΛΜΛβΛΈΛΗΛψΓΔΛ»ΛΤΛβΛ≥ΛλΛάΛ±ΛΈΙβΛœΛ«Λ ΛΛΓΙ
ΓΗΛΣΛΗΛΒΛσΓΘΛΛΛΟΛΩΛΛΛ…ΛΈΛ·ΛιΛΛΛΈ²éΛΠΛΝΛ§ΛΔΛκΛΈΘΩΓΙ
ΓΗ»ΐΧΪΓΔΛΫΓΔΛΫΛλΛœΛύΛξΛάΓΘΛ»ΛΤΛβ”΄ΥψΛ«Λ≠ΛκΛβΛΈΛΗΛψΛ ΛΛΓΘΚΈ °ÉΘϋΛΪΓΔΚΈΑΌÉΘϋΛΪΓ≠Γ≠Λ≥ΛλΛάΛ±ΛΈ¥σΛ≠ΛΒΛΈΛ≥ΛλΛάΛ±ΛΈΝΘΛΈΛΫΛμΛΟΛΩΓΔ²ϊΛΈΛ ΛΛΞάΞΛΞδΞβΞσΞ…ΛœΓΔ άΫγΛΥΛΦΛΟΛΩΛΛΛΥνêΛ§Λ ΛΛΛσΛάΓΙ
ΓΓΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛ§ΓΔöίΛ§Λ·ΛκΛΛΛΫΛΠΛΥΥΦΛΟΛΩΛΈΛβΛύΛξΛœΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΞάΞΛΞδΞβΞσΞ…ΛΈΛηΛΠΛ ±Π ·νêΛρΛœΛΪΛκΛΥΛœΓΔΞΪΞιΞΟΞ»Λ»ΛΛΛΠÖgΈΜΛ§ ΙΛοΛλΛκΛΈΛάΛ§ΓΔ“ΜΞΪΞιΞΟΞ»Λœ©•Θ°ΕΰΞΑΞιΞύΓΘΛ≥ΛλΛάΛ±ΛΈΞάΞΛΞδΛ ΛιΓΔ…ΌΛ Λ·Λ»ΛβΕΰΑΌΞΪΞιΞΟΞ»ΛœΛΔΛκΛ≥Λ»ΛάΛμΛΠΓΘ
ΓΓΛΛΛόΛόΛ«ΛΥΑk“äΛΒΛλΛΩΓΔ άΫγΉν¥σΛΈΞάΞΛΞδΞβΞσΞ…ΛœΓΔΨ≈ΤΏ“ΜΞΪΞιΞΟΞ»Λ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΛ§ΓΔΛ≥ΛλΛœΘϋ‘≠ΓΕΛ≤ΛσΓΖΘϋ ·ΓΕΛΜΛ≠ΓΖΛΈ¥σΛ≠ΛΒΛ«ΓΔΦ”ΙΛΛΒΛλΛΩΛξΓΔ–ΓΛΒΛ·«–ΛιΛλΛΩΛξΛΙΛκΛΈΛ«ΓΔΆξ≥…ΛΒΛλΛΩΛβΛΈΛ»ΛΖΛΤΛœΓΔ”ΔΙζΜ “ΛΥΟΊ iΛΒΛλΛκΓΚ…ΫΛΈΙβΓΜΛΈ“Μ©•ΝυΞΪΞιΞΟΞ»Λ§ άΫγΉν¥σΛ»ΛΛΛοΛλΛΤΛΛΛκΛΈΛάΓΘ
ΓΓ“ΜΞΪΞιΞΟΞ»Λ«ΛβΓΔΛΫΛΠΛ»ΛΠΗΏΛΛ²éΕΈΛ ΛΈΛάΛΪΛιΓΔΛΫΛλΛ§ΓΔ¥σΛ≠Λ·Λ ΛλΛ–Λ ΛκΛέΛ…ΓΔΛ»ΛσΛ«ΛβΛ ΛΛ²éΕΈΛΥΛ ΛΟΛΤΛ·ΛκΛΈΛάΓΘΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛ§ΛΛΛόΓΔΚΈ °ÉΘϋΛΪΚΈΑΌÉΘϋΛ»ΛΛΛΟΛΩΛΈΛβΓΔΛ±ΛΟΛΖΛΤΛΠΛΫΛ«ΛœΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛ»ΈΡ―εΛœΓΔœΔΛρΛΈΛσΛ«œδΛΈΛ ΛΪΛρ“äΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΛ»Λ≠ΛάΛΟΛΩΓΘ»ΐΧΪΛ§Λ»ΛΡΛΦΛσΓΔΛ»ΛσΛ≠ΛγΛΠΛ …υΛρΛΔΛ≤ΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΗΛΣΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛ≥ΓΔΛ≥ΛλΛΗΛψΛΔΛξΛόΛΜΛσΛΪΓΘΛ≥ΛΈΞάΞΛΞδΛΗΛψΛΔΛξΛόΛΜΛσΛΪΓΙ
ΓΓ»ΐΧΪΛ§“äΛΡΛ±ΛΩΛΈΛœΓΔ°£ΛΈ…œΛΥΆΕΛ≤ΛάΛΖΛΤΛΔΛΟΛΩœΠΩ·ΛάΛΟΛΩΓΘΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛ»ΈΡ―εΛœΓΔ»ΐΧΪΛΈ÷ΗΛΒΛΙΛ»Λ≥ΛμΛρ“äΛΤΓΔΛΣΛβΛοΛΚΞΔΞΟΛ»œΔΛρΛΈΛΏΛ≥ΛσΛάΓΘ
ΘέΘΘΛ≥Λ≥ΛΪΛιΘ±Ή÷œ¬Λ≤Θί
ΓΑ άΫγΒΡΘϋ¥σΓΕΛάΛΛΓΖΘϋ±ΠΓΕΛέΛΠΓΖΘϋΙΎΓΕΛΪΛσΓΖœϊΛφΘΓΓ≠Γ≠Ι÷ΒΝΓΔψy¹ΔΟφΛΈΛΖΛοΛΕΓ≠Γ≠ïr¹ΐ ΐΑΌÉΘϋÉ“ΓΔΞ ΞΨΛρΛΡΛΡΛύΝυΛΡΛΈΞάΞΛΞδΓ≠Γ≠Γ±
ΘέΘΘΛ≥Λ≥Λ«Ή÷œ¬Λ≤ΫKΛοΛξΘί
ΓΓΛΫΛσΛ Λ≥Λ»Λ–Λ§ΝυΕΈΛΧΛ≠ΛΈ¥σ“ä≥ωΛΖΓΔ¥σΛ≠Λ ΜνΉ÷Λ«ïχΛΛΛΤΛΔΛκΛΈΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ»ΐ»ΥΛœœΔΛρΛΈΛσΛ«ΓΔüo―‘ΛΈΛόΛόΓΔΛΖΛ–ΛιΛ·Λ≥ΛΈΜνΉ÷ΛρΛΥΛιΛσΛ«ΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ¥σ±ΠΙΎ
ΓΑ άΫγΒΡ¥σ±ΠΙΎœϊΛφΘΓΓ≠Γ≠Ι÷ΒΝΓΔψy¹ΔΟφΛΈΛΖΛοΛΕΓ≠Γ≠ïr¹ΐ ΐΑΌÉΘϋÉ“ΓΔΞ ΞΨΛρΛΡΛΡΛύΝυΛΡΛΈΞάΞΛΞδΓ≠Γ≠Γ±
ΓΓΛΔΛΔΓΔΛ“ΛγΛΟΛ»ΛΙΛκΛ»Λ≥ΛΈ ¬ΦΰΛ»ΓΔΈΡ―εΛΈΛβΛιΛΟΛΩΜΤΫπΛΈ–ΓœδΛ»ΛΈΛΔΛΛΛάΛΥΛœΓΔΛ ΛΥΛΪιv²SΛ§ΛΔΛκΛΈΛ«ΛœΛΔΛκΛόΛΛΛΪΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛœΛΒΛΤΛΣΛ≠ΓΔΛΫΛΈ“ΙΛœ»ΐ»ΥΛΛΛΟΛΖΛγΛΥΓΔΟΏΛιΛλΛΧ“Μ“ΙΛρΛΙΛ¥ΛΖΛΩΛ§ΓΔ“ΙΟςΛ±Λρ¥ΐΛΟΛΤΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛ§ΓΔΈΡ―εΛδ»ΐΧΪΛρΏBΛλΛΤΓΔΛδΛΟΛΤΛ≠ΛΩΛΈΛœΘϋ½@ΧοιTΓΕΛΒΛ·ΛιΛάΛβΛσΓΖΛΈΨ·“ïéΊΓΘΘϋΒ»ΓΕΛ»ΓΖΘϋΓ©ΓΕΛ…ΓΖΘϋΝΠΓΕΛμΛ≠ΓΖΨ·≤ΩΛΥΜαΛΛΛΩΛΛΛ»ΛΛΛΠΛ»ΓΔΛΙΛΑèξΫ” “ΛΥΆ®ΛΒΛλΛΤΓΔ¥ΐΛΡιgΛέΛ…Λ Λ·ΛΔΛιΛοΛλΛΩΛΈΛœΓΔΥΡ °ΈεΓΔΝυörΛΈΘϋ―Σ…ΪΓΕΛ±ΛΟΛΖΛγΛ·ΓΖΛΈΛηΛΛ»ΥΈοΓΘΛΫΛλ˧»éΝΠΨ·≤ΩΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΗΛδΛΔΓΔΫπΧο“ΜΛΒΛσΓΔΛΖΛ–ΛιΛ·ΓΘΛΣΛδΛΣΛδΓΔΛ≠ΛγΛΠΛœΛΏΛγΛΠΛ ΏBΛλΛ»ΛΛΛΟΛΖΛγΛ«ΛΙΛΆΓΙ
ΓΓΨ·≤ΩΛœΛ’ΛΖΛ°ΛΫΛΠΛ νÜΛρΛΖΛΤΓΔΈΡ―εΛ»»ΐΧΪ…ΌΡξΛρ“äΛ·ΛιΛΌΛΤΛΛΛκΓΘΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛœΛ’ΛΩΛξΛρΨ·≤ΩΛΥΛ“Λ≠ΛΔΛοΛΜΛκΛ»ΓΔ
ΓΗΛΗΛΡΛœΓΔΨ·≤ΩΛΒΛσΓΔΛ≠ΛγΛΠΛ≠ΛΩΛΈΛœΛέΛΪΛ«ΛβΛΔΛξΛόΛΜΛσΓΘψy¹ΔΟφΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΙΛ§ΛΆΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛ§ΩΎΛρΛ“ΛιΛΛΛΩΛ»ΛΩΛσΓΔΨ·≤ΩΛœΛ“ΛΕΛρΛΈΛξΛάΛΖΛΤΓΔ
ΓΗΫπΧο“ΜΛΒΛσΓΔΛΫΛΈΛ≥Λ»Λ ΛιΓΔΛ≥ΛΝΛιΛΪΛιΛ¥œύ’³ΛΥΛΔΛ§ΛμΛΠΛ»ΥΦΛΟΛΤΛΛΛΩΛ»Λ≥ΛμΛ«ΛΙΓΘΛΛΛδΛβΛΠΛΩΛΛΛΊΛσΛ’ΛΖΛ°Λ ¬ΦΰΛ«ΛΖΛΤΛΆΓΙ
ΓΗΛΫΛΠΛιΛΖΛΛΛ«ΛΙΛΆΓΘ–¬¬³Λ«Λ“Λ»Λ»ΛΣΛξ’iΛσΛ«ΛœΛΣΛξΛόΛΙΛ§ΓΔΛ…ΛΠΛ«ΛΖΛγΛΠΓΘΛβΛΠ“ΜΕ»ΓΔΛ·ΛοΛΖΛ·ΛΣ‘£ΛΖΛΆΛ§Λ®ΛόΛΜΛσΛΪΓΙ
ΓΗΛΛΛΛΛ«ΛΙΛ»ΛβΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛΫΛ≥Λ«Ψ·≤ΩΛ§‘£ΛΖΛάΛΖΛΩΛΈΛœΓΔΛΡΛ°ΛΈΛηΛΠΛ Λ’ΛΖΛ°Λ ¬ΦΰΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ»’±ΨΛ«Λβ÷ΗΛΣΛξΛΈ±Π ·ΆθΛ»ΛΛΛοΛλΛκΓΔΘϋΦ”ΓΕΛΪΓΖΘϋΧΌΓΕΛ»ΛΠΓΖΘϋ±ΠΓΕΛέΛΠΓΖΘϋΉςΓΕΛΒΛ·ΓΖάœ»ΥΛΈΛβΛ»ΛΊΓΔ άΫγΒΡ¥σ±ΠΙΎΛρΛΣΛφΛΚΛξΛΖΛΩΛΛΛ»ΛΛΛΠ ÷ΦàΛ§ΛόΛΛΛ≥ΛσΛάΛΈΛœΓΔΥΡΓΔΈε»’ΛόΛ®ΛΈΛ≥Λ»ΛάΛΟΛΩΓΘ ÷ΦàΛΈΛ ΛΪΛΥΛœΓΔΚΈΟΕΛΪΛΈ–¥’φΛ§ΛœΛΛΛΟΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈ–¥’φΛρ“ΜΡΩ“äΛΩΛ»Λ≠ΓΔΛΒΛΙΛ§ΛΈ±ΠΉςάœ»ΥΛβΓΔΥΦΛοΛΚΞΠ©Γ°ΞύΛ»ΛΠΛ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛ≥ΛΥΛΠΛΡΛΟΛΤΛΛΛκΛΈΛœΓΔ άΛΥΛβ’δΛΖΛΛΆθΙΎΛάΛ§ΓΔ±ΠΉςάœ»ΥΛ§ΛΠΛ ΛΟΛΩΛΈΛœΓΔΛΫΛΈΆθΙΎΛΥΗ––ΡΛΖΛΩΛΩΛαΛ«ΛœΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘΛΫΛΈΆθΙΎΛΥΛΝΛξΛ–ΛαΛιΛλΛΤΛΛΛκΓΔΝυΛΡΛΈΞάΞΛΞδΛΈ¥σΛ≠ΛΒΛ ΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΛΛόΛόΛ« άΫγΛ«÷ΣΛιΛλΛΤΛΛΛκΓΔΛ…ΛσΛ ΞάΞΛΞδΛάΛΟΛΤΓΔΉψΛβΛ»ΛΥΛβΛΣΛηΛ–ΛΧΛηΛΠΛ ¥σΝΘΞάΞΛΞδΓΘΛβΛΖΛβΓΔΛ≥ΛλΛ§±ΨΈοΛ»ΛΙΛλΛ– άΫγΛΥΕΰΛΡΛ»Λ ΛΛ¥σ±ΠΙΎΛ ΛΈΛάΓΘ±ΠΉςάœ»ΥΛœΛβΛΠΛέΛΖΛ·ΛΤΛΩΛόΛιΛ Λ·Λ ΛΟΛΩΛ§ΓΔΛΫΛλΛ«Λβ”Ο–ΡΛ÷ΛΪΛΛάœ»ΥΛΈΛ≥Λ»ΛάΛΪΛιΓΔΛΗΛ÷ΛσΛ§Λ«ΛΪΛ±ΛΤΛΛΛ·ΛόΛ®ΛΥΓΔΡΩΛΈΛ≠ΛΛΛΩ÷ß≈δ»ΥΛρΛΒΛΖΛύΛ±ΛΩΓΘ
ΓΓΛ»Λ≥ΛμΛ§ΓΔΛΫΛΈ÷ß≈δ»ΥΛβΓΔΛΙΛΟΛΪΛξΛΣΛ…ΛμΛΛΛΤéΔΛΟΛΤΛ≠ΛΩΓΘΛΫΛλΛœΛΩΛΖΛΪΛΥ±ΨΈοΛάΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘΛΔΛΈ¥σΛ≠ΛΒΓΔΛΔΛΈΛΏΛ¥Λ»ΛΒΛ«ΛœΓΔΛΠΛΩΛ§ΛΛΛβΛ Λ·ΓΔΚΈ °ÉΘϋΓΔΚΈΑΌÉΘϋΛ»ΛΛΛΠ²éΛΠΛΝΛΈΤΖΈοΛάΛ»ΛΛΛΠΛΈΛάΓΘ
ΓΓΛΒΛΔΓΔ±ΠΉςάœ»ΥΛœΛΫΛλΛ§ΛέΛΖΛ·ΛΤΛΩΛόΛιΛ Λ·Λ ΛΟΛΩΓΘ»ΪΊî°bΛρΆΕΛ≤ΛάΛΖΛΤΛβΓΔΛΫΛλΛρ ÷ΛΥΛΛΛλΛΩΛΛΛ»ΥΦΛΛΛ≥ΛσΛάΛΈΛάΓΘΛΖΛΪΛΖΓΔΛΫΛλΛ»Ά§ïrΛΥΓΔ±ΠΉςάœ»ΥΛ§Λ’ΛΖΛ°Λ«ΛΩΛόΛιΛ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛœΓΔΛΫΛΈ¥σ±ΠΙΎΛΈ≥ωΛ…Λ≥ΛμΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ±ΠΉςάœ»ΥΛœ¨üιTΦ“ΛΈΛ≥Λ»ΛάΛΪΛιΓΔ άΫγΒΡΛ ΞάΞΛΞδΛœΛΏΛσΛ ÷ΣΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΛ…Λ≥ΛΥΛ…ΛσΛ ΞάΞΛΞδΛ§ΛΔΛκΛΪΓΔΛ…Λ≥ΛΈΞάΞΛΞδΛœΛ…ΛΈΛ·ΛιΛΛΛΈ¥σΛ≠ΛΒΛΪΓΔΛΫΛσΛ Λ≥Λ»ΛρΓΔΛΙΛΏΛΪΛιΛΙΛΏΛόΛ«÷ΣΛΟΛΤΛΛΛκΛΈΛάΓΘΛΖΛΪΛΖΛ≥ΛσΛ…ΛΈΞάΞΛΞδΛΈΛηΛΠΛ ΛβΛΈΛœΓΔΛΛΛόΛόΛ«“ΜΕ»ΛβΛ≠ΛΛΛΩΛ≥Λ»Λ§Λ ΛΪΛΟΛΩΓΘΛάΛΛΛΛΛΝΓΔΛ≥ΛλΛάΛ±ΝΘΛΈΛΫΛμΛΟΛΩ¥σΛ≠Λ ΞάΞΛΞδΛœΓΔΛόΛάös ΖΛΥΛΔΛιΛοΛλΛΩΛ≥Λ»Λ§Λ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓ±ΠΉςάœ»ΥΛœΛβΛΠ“ΜΕ»ΓΔΛΗΛ÷ΛσΛΈΡΩΛ«ΛΩΛΖΛΪΛαΛΤΛΏΛΩΛΛΛ»ΥΦΛΟΛΩΓΘΛΫΛ≥Λ«ΓΔΛΛΛμΛΛΛμΫΜ€hΛΖΛΩΛΔΛ≤Λ·ΓΔ÷ß≈δ»ΥΛ»ΛΛΛΟΛΖΛγΛΥΓΔΛβΛΠ“ΜΕ»ΓΔ¥σ±ΠΙΎΛρ“äΛΜΛΤΛβΛιΛΠΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛξΓΔœ»ΖΫΛΈ÷ΗΕ®ΛΈàωΥυΛΊΛΈΛξΛ≥ΛσΛάΛ§ΓΔΛΫΛλΛ§Λ≠ΛΈΛΠΛΈΛ≥Λ»Λ ΛΈΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ °Εΰ²ÄΛΈΞάΞΛΞδ
ΓΓΛΫΛΈàωΥυΛ»ΛΛΛΠΛΈΛœΓΔ–¬ΥόΛΥΛΔΛκ–ΓΛΒΛ ΞέΞΤΞκΛΈ“Μ “ΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓœ»ΖΫΛΈΡ–Λ»ΛΛΛΠΛΈΛœΓΔ±≥ΛΈΒΆΛΛΓΔ»ΥœύΛΈΛηΛ·Λ ΛΛ»ΥΈοΛ«ϋΛαΛ§ΛΆΛρΛΪΛ±ΛΤΛΛΛκΛ»Λ≥ΛμΛ§ΓΔΛΛΛΪΛΥΛβΛΠΛΒΛσΛ·ΛΒΛΛΘέΘΘΓΗΛΠΛΒΛσΛ·ΛΒΛΛΓΙΛΥΑχΒψΘίΗ–ΛΗΛ§ΛΖΛΩΓΘΛΣΛόΛ±ΛΥΛ ΛΥΛΥΛΣΛ”Λ®ΛκΛΈΛΪΓΔΛΖΛΗΛεΛΠΛ”Λ·Λ”Λ·ΛΖΛΤΛΛΛκΛ»Λ≥ΛμΛ§ΓΔ±ΠΉςάœ»ΥΛΥΛβΛΛΛΟΛΫΛΠΛΔΛδΛΖΛ·ΥΦΛοΛλΛΩΓΘΟϊΛόΛ®ΛœΘϋΦöΓΕΛέΛΫΓΖΘϋ¥®ΓΕΛΪΛοΓΖΘϋΦΣΓΕΛηΛΖΓΖΘϋ–έΓΕΛΣΓΖΛ»ΛΛΛΟΛΩΛ§ΓΔΛ≥ΛλΛœ±ΨΟϊΛΪΛ…ΛΠΛΪΛοΛΪΛιΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΝυ²ÄΛΈΞάΞΛΞδΛœ±ΨΈοΛάΛΟΛΩΓΘ±ΠΉςάœ»ΥΛ§ΛΔΛιΛφΛκ÷ΣΉRΛρΛ’ΛξΛΖΛήΛΟΛΤ’ΘϊΛΌΛΤΛΏΛΤΛβΓΔΛ…ΛΠΛΖΛΤΛβ±ΨΈοΛ»ΛΖΛΪΥΦΛ®Λ ΛΛΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘœύ ÷ΛΈ‘£ΛΥΛηΛκΛ»ΓΔΛΫΛΈ¥σ±ΠΙΎΛœΓΔΞ®ΞΗΞΉΞ»ΆθΦ“ΛΥ¥ζΓ©¹ΜΛ®ΛιΛλΛΤΛΛΛΩΛβΛΈΛ«ΓΔΛΔΛΈ”–ΟϊΛ ΞΫΞμΞβΞσΆθΛΈ±ΠΈοΛάΛ»ΛΛΛΠΛΈΛάΛ§ΓΔΛ≥ΛλΛœΛΔΛόΛξΛΔΛΤΛΥΛ ΛιΛ ΛΛΓΘΒΎ“ΜΓΔΜΤΫπΛΈΧ®ΉυΛΈΦöΙΛΛρ“äΛΤΛβΓΔΛΡΛΛΫϋΛ¥ΛμΓΔΛΡΛ·ΛιΛλΛΩΛβΛΈΛ»ΛΖΛΪΥΦΛ®Λ ΛΛΛΈΛάΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΞάΞΛΞδΛœ±ΨΈοΛάΛΪΛιΓΔ±ΠΉςάœ»ΥΛœΛΈΛ…ΛΪΛι ÷Λ§≥ωΛκΛέΛ…ΛέΛΖΛ·Λ ΛΟΛΩΓΘΛΫΛ≥Λ«ΓΔΛΛΛμΛΛΛμΛ ²éΕΈΛΈΛΪΛ±Λ“Λ≠Λ§ΛœΛΗΛόΛΟΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΆΨ÷–Λ«±ΠΉςάœ»ΥΛœΓΔϋΛαΛ§ΛΆΛΈΡ–ΛρΛΫΛ≥ΛΥ≤–ΛΖΛΤΓΔ÷ß≈δ»ΥΛ»Λ’ΛΩΛξΛ«ΓΔκOΛΈΛΊΛδΛΊΛ“Λ≠ΛΒΛ§ΛΟΛΩΓΘΛΫΛΖΛΤΓΔΛΔΛλΛδΛ≥ΛλΛδΛ»œύ’³ΛΖΛΤΛΛΛκΛ»Λ≥ΛμΛΊΓΔΛάΛΖΛΧΛ±ΛΥΓΔκOΛΈΛΊΛδΛΪΛ鬳Λ≥Λ®ΛΤΛ≠ΛΩΛΈΛ§ΓΔΩ÷ΛμΛΖΛΛΡ–ΛΈ±·χQΛάΛΟΛΩΛΈΛάΓΘ
ΓΓ±ΠΉςάœ»ΥΛ»÷ß≈δ»ΥΛœΓΔΛΣΛ…ΛμΛΛΛΤΓΔΛΒΛΪΛΛΛΈΞ…ΞΔΛΥΛ»Λ”ΛΡΛΛΛΩΛ§ΓΔΛ’ΛΖΛ°Λ Λ≥Λ»ΛΥΛΫΛΈΞ…ΞΔΛΥΛœΓΔΛύΛ≥ΛΠΛΪΛιΞΪΞ°Λ§ΛΪΛΪΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛρΛύΛξΛΥΛΠΛΝΛδΛ÷ΛΟΛΤΓΔΛ ΛΪΛΊΛ»Λ”Λ≥ΛσΛ«ΛΏΛκΛ»ΓΔϋΛαΛ§ΛΆΛΈΡ–Λ§―ΣΛόΛΏΛλΛΥΛ ΛΟΛΤΒΙΛλΛΤΛΛΛκΓΘ“äΛκΛ»ΓΔ±≥÷–ΛΥδ³ΛΛΕΧΒΕΛ§ΛΡΛΟΝΔΛΟΛΤΛΣΛξΓΔΛύΛμΛσΓΔœΔΛœΛ ΛΛΓΘ
ΓΓ±ΠΉςάœ»ΥΛœΛΣΛ…ΛμΛΛΛΤΓΔΛΔΛΩΛξΛρ“äΛόΛοΛΖΛΩΛ§ΓΔΛΒΛΟΛ≠ΛόΛ«ΓΔΞΤ©Γ°Ξ÷ΞκΛΈ…œΛΥΛΔΛΟΛΩ¥σ±ΠΙΎΛ§ΓΔ”ΑΛβ–ΈΛβ“äΛΔΛΩΛιΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛβΓΔΆβΛΥΛύΛΪΛΟΛΩΖôΛ§ΛΔΛΛΛΤΛΛΛκΛ»Λ≥ΛμΛρ“äΛκΛ»ΓΔΛάΛλΛΪΛ§ΛΫΛ≥ΛΪΛιΛΖΛΈΛ”Λ≥ΛΏΓΔϋΛαΛ§ΛΆΛΈΡ–ΛρöΔΛΖΛΤΓΔ¥σ±ΠΙΎΛρΛΠΛ–ΛΟΛΤΧ”Λ≤ΛΩΛΥΛΝΛ§ΛΛΛ ΛΛΛΈΛάΛ§ΓΔΛ’ΛΖΛ°Λ ΛΈΛœΓΔϋΛαΛ§ΛΆΛΈΡ–ΛΈ±≥÷–ΛΥΛΡΛΟΝΔΛΟΛΤΛΛΛκΕΧΒΕΛάΛΟΛΩΓΘΛΫΛλΛœΦöΛΛΓΔΞαΞΙΛΈΛηΛΠΛ ΕΧΒΕΛ ΛΈΛάΛ§ΓΔΛηΛ·“äΛκΛ»ΓΔΛΡΛ–ΛΥΛΔΛΩΛκΛ»Λ≥ΛμΛΥΓΔΛΏΛγΛΠΛ ΛβΛΈΛ§ΛΡΛ≠ΛΒΛΖΛΤΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΗΛΫΛλΛ§ΓΔΛΙΛ ΛοΛΝΓΔΛ≥ΛλΛ ΛσΛ«ΛΙΛ§ΛΆΓΙ
ΓΓ’ZΛξΛΣΛοΛΟΛΤΓΔΨ·≤ΩΛ§Λ»ΛξΛάΛΖΛΤ“äΛΜΛΩΛβΛΈΛρ“äΛΤΓΔΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛρΛœΛΗΛαΛ»ΛΖΛΤΈΡ―εΛβ»ΐΧΪ…ΌΡξΛβΓΔΥΦΛοΛΚΞΔΞΟΛ»œΔΛρΛΈΛΏΛ≥ΛσΛάΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛœ“ΜΟΕΛΈΞ»ΞιΞσΞΉΓΔΞάΞΛΞδΛΈΞίΞΛΞσΞ»Θ®Θ±Θ©Λ ΛΈΛάΛ§ΓΔ÷–―κΛΥΞΑΞΒΞΟΛ»―®Λ§ΛΔΛ≠ΓΔΛΖΛΪΛβΓΔΛΑΛΟΛΖΛγΛξ―ΣΛΥΛΧΛλΛΤΛΛΛκΛ«ΛœΛ ΛΛΛΪΓΘ»ΐΧΪΛ»ΈΡ―εΛœΥΦΛοΛΚΛ’ΛκΛ®ΛΔΛ§ΛΟΛΩΓΘ
ΓΗΛΡΛόΛξϋΛαΛ§ΛΆΛΈΡ–ΛρöΔΛΙΛόΛ®ΛΥΓΔΕΧΒΕΛ«Λ≥ΛΈΞ»ΞιΞσΞΉΛρΛΒΛΖΛΡΛιΛΧΛ≠ΓΔΛΫΛλΛ«ΛβΛΟΛΤΓΔΞΑΞΒΞΟΛ»ϋΛαΛ§ΛΆΛΈΡ–ΛρΛΒΛΖöΔΛΖΛΩΛΥΛΝΛ§ΛΛΛ ΛΛΛΈΛ«ΛΙΛ§ΓΔΛΫΛλΛ«ΛœΓΔΛ ΛΦΓΔΛΫΛσΛ ΛΏΛγΛΠΛ ΛόΛΆΛρΛΖΛΩΛΪΛ»ΛΛΛΠΛ»ΓΔΛΫΛλΛΥΛΡΛΛΛΤΥΦΛΛΛάΛΒΛλΛκΛΈΛœψy¹ΔΟφΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΙΓΙ
ΓΗψy¹ΔΟφΓ≠Γ≠ΓΙ
ΓΓΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛœΛΒΛΑΛκΛηΛΠΛΥΓΔΨ·≤ΩΛΈνÜΛρ“äΛΤΛΛΛκΓΘΈΡ―εΛ»»ΐΧΪ…ΌΡξΛβΓΔΛ≠ΛσΛΝΛγΛΠΛΖΛΤΓΔœΔΛρΛΈΛσΛ«ΛΛΛΩΓΘ
ΓΗΛΫΛΠΛ«ΛΙΓΘΫπΧο“ΜΛΒΛσΓΔΛΔΛ ΛΩΛœΛΣ¬³Λ≠ΛΥΛ ΛΟΛΩΛ≥Λ»Λ§ΛΔΛξΛόΛΜΛσΛΪΓΘΛΛΛόΛΪΛι °ΚΈΡξΛΪΛόΛ®ΛΥΓΔœψΗέΛΥψy¹ΔΟφΛ»ΛΛΛΠΙ÷ΒΝΛ§ΛΔΛιΛοΛλΛΩΛ≥Λ»Λ§ΛΔΛξΛόΛΙΓΘΛΫΛΈ’ΐΧεΛœΓΔΛΛΛόΛΥΛΛΛΩΛκΛβΛοΛΪΛξΛόΛΜΛσΛ§ΓΔΛΛΛΡΛβψy…ΪΛΥΙβΛκΛΣΟφΛρΛΪΛ÷ΛΟΛΤΛΛΛΤΓΔΛΆΛιΛΠΛβΛΈΛ»ΛΛΛ®Λ–±Π ·Λ–ΛΪΛξΓΘΛΖΛΪΛβΓΔΛΫΛΛΛΡΛ§ΛΔΛιΛοΛλΛΩΛΔΛ»ΛΥΛœΓΔΛ≠ΛΟΛ»Ξ»ΞιΞσΞΉΛΈΞάΞΛΞδΛΈΛ’ΛάΛ§≤–ΛΟΛΤΛΛΛΩΛΈΛ«ΛΙΓΙ
ΓΓΫπΧο“ΜΗϊ÷ζΛœΈΡ―εΛδ»ΐΧΪ…ΌΡξΛ»νÜΛρ“äΚœΛοΛΜΛΩΓΘΨ·≤ΩΛœΛ ΛΣΛβΛ≥ΛΈΛ≥Λ»Λ–ΛρΛΡΛΛΛ«ΓΔ
ΓΗΛΫΛλΛ–ΛΪΛξΛ«ΛœΛ Λ·ΓΔψy¹ΔΟφΛΥΛœ÷ΌιgΛ»ΛΛΛΠΛΪΓΔΉ”Ζ÷Λ»ΛΛΛΠΛΪΓΔΛΫΛΠΛΛΛΠΏB÷–Λ§ΛΩΛ·ΛΒΛσΛΔΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΙΛ§ΓΔΛβΛΖΓΔΛΫΛλΛιΛΈΏB÷–Λ§ΓΔψy¹ΔΟφΛΈΟϋΝνΛΥΛΫΛύΛΛΛΩΛξΓΔ―Y«–ΛΟΛΩΛξΛΙ