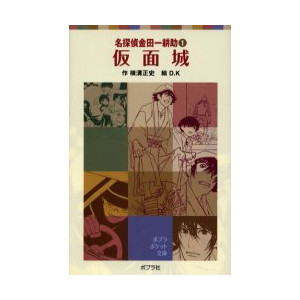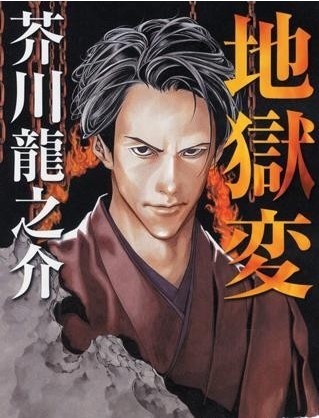¹ΔΟφ≥«(»’ΈΡΑφ)-ΒΎ26’¬
Α¥Φϋ≈Χ…œΖΫœρΦϋ Γϊ Μρ Γζ Ω…ΩλΥΌ…œœ¬Ζ≠“≥Θ§Α¥Φϋ≈Χ…œΒΡ Enter ΦϋΩ…ΜΊΒΫ±Ψ ιΡΩ¬Φ“≥Θ§Α¥Φϋ≈Χ…œΖΫœρΦϋ Γϋ Ω…ΜΊΒΫ±Ψ“≥ΕΞ≤ΩΘΓ
ΓΣΓΣΓΣΓΣΈ¥‘ΡΕΝΆξΘΩΦ”»κ ι«©“―±ψœ¬¥ΈΦΧ–χ‘ΡΕΝΘΓ
ΛηΓΙ
ΓΗΛ ΓΔΛ ΛσΛ«ΛΙΛΟΛΤΓΙ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛΣΛ…ΛμΛΛΛΤΗΗΛΈνÜΛρ“äΛ ΛΣΛΖΛΩΓΘ
ΓΗΛύΛμΛσΓΔΛœΛΗΛαΛΪΛιΛΫΛΈΛΡΛβΛξΛΗΛψΛ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛάΛ§ΓΔΫYΙϊΛΥΛΣΛΛΛΤΛΫΛΠΛ ΛΟΛΩΛΈΛάΓΘΟάΖΘßΉ”ΓΔΛόΛΔ¬³ΛΛΛΤΛΣΛ·ΛλΓΙ
ΓΓΛΫΛ≥Λ«ΉΎœώ≤© ΩΛ§‘£ΛΖΛΩΛΈΛœΓΔΛΡΛ°ΛΈΛηΛΠΛ ΛΕΛσΛ≤ΘέΘΘΓΗΛΕΛσΛ≤ΓΙΛΥΑχΒψΘί‘£ΛάΓΘ
ΓΓάθ…ζèΊ‘’Λ»ΉΎœώ≤© ΩΛ»ΛœΛΫΛΈΛύΛΪΛΖΓΔ”H”―ΛάΛΟΛΩΓΘΛ≥ΛΈάθ…ζΛ»ΛΛΛΠΡ–ΛœΫπ≥÷ΛΝΛΈΛΣΖΜΛΝΛψΛσΛάΛΟΛΩΛ§ΓΔ”HνêΛ»ΛΛΛΠΛβΛΈΛ§Λ“Λ»ΛξΛβΛ Λ·ΓΔΛΫΛλΛ«Ίî°bΛΈΙήάμΛ Λ…ΛβΛΛΛΟΛΒΛΛΓΔΉΎœώ≤© ΩΛΥΛόΛΪΛΜΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΛΠΛΝΛΥΛΪΛλΛœΛΣΛ·ΛΒΛσΛρΛβΛιΛΟΛΤΉ”Λ…ΛβΛ§…ζΛόΛλΛΩΓΘΛΫΛλΛ§ΛΡΛόΛξΒά÷°÷ζΛ ΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘΛ»Λ≥ΛμΛ§Λ≥ΛΈΒά÷°÷ζΛ§ΕΰΛΡΛΥΛ ΛΟΛΩΛ»Λ≠ΓΔάθ…ζΛœΫYΚΥΛ«ΥάΛσΛάΛΈΛάΛ§ΓΔΛΫΛΈΥάΛΈιgΛ°ΛοΛΥΓΔΛΔΛ»ΛΈΛ≥Λ»ΛρΉΎœώ≤© ΩΛΥΛΩΛΈΛσΛ«ΛΛΛΟΛΩΓΘΛύΛμΛσ≤© ΩΛœ”H”―ΛΈΏz―‘Λρ ΊΛκΛΡΛβΛξΛάΛΟΛΩΛ§ΓΔΛΩΛάΛ≥ΛόΛΟΛΩΛ≥Λ»ΛΥΛœΒά÷°÷ζΛΈΡΗΛ»ΛΛΛΠΛΈΛ§ΓΔΛ»ΛΤΛβΛΩΛΝΛΈΛοΛκΛΛ≈°Λ«ΓΔΛΠΛΪΛΡΛΥΊî°bΛ Λ…Ε…ΛΜΛ ΛΛΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΫΛ≥Λ«ΉΎœώ≤© ΩΛœΓΔΒά÷°÷ζΛ§¥σΛ≠Λ·Λ ΛκΛόΛ«Ίî°bΛρ±ΘΙήΛΖΛΤΛΛΛηΛΠΛ»ΥΦΛΛΓΔΛ≥Λ»Λ–ΛρΛΔΛΛΛόΛΛΛΥΛΥΛ¥ΛΖΛΤΓΔΡΗ”HΛΈΛΛΛΠΛ≥Λ»Λρ»ΓΛξΛΔΛ≤ΛΚΛΥΛΣΛΛΛΩΓΘΛΙΛκΛ»œύ ÷ΛœΓΔΛΤΛΟΛ≠Λξ≤© ΩΛ§Ίî°bΛρΉ‘Ζ÷ΛΈΛβΛΈΛΥΛΙΛκΛΡΛβΛξΛάΛμΛΠΛ»‘γΛ§ΛΤΛσΛΖΛΤΓΔΛ≥ΛΈèΆΛΖΛεΛΠΛœΛΪΛ ΛιΛΚΛΙΛκΛΪΛιΛΣΛήΛ®ΛΤΛΛΛμΛ»ΓΔΛβΛΈΛΙΛ¥ΛΛΛΣΛ…ΛΖΛβΛσΛ·Λρ≤–ΛΖΛΤΓΔΛΫΛλΛΪΛιιgΛβΛ Λ·Ή”Λ…ΛβΛ»Λ»ΛβΛΥΓΔΛΙΛ§ΛΩΛρΛ·ΛιΛόΛΖΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘΛ ΛΥΛΖΛμΛΫΛΈ≈°ΛœΓΔΛόΛά’ΐ ΫΛΥάθ…ζΛΈΤόΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛ«ΓΔΖ®¬…Λ«ΛΔΛιΛΫΛΠΛοΛ±ΛΥΛβΛΛΛΪΛ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛάΓΘ
ΓΓΉΎœώ≤© ΩΛœΛύΛμΛσααΜΎΛΖΛΩΓΘΡΗ”HΛœΡΗ”HΛ»ΛΖΛΤΓΔΉ”Λ…ΛβΛœάθ…ζΛΈΉ”ΛΥΛΝΛ§ΛΛΛ ΛΛΛΈΛάΛΪΛιΓΔΛ ΛσΛ»ΛΪΛΖΛΤΛΒΛ§ΛΖ≥ωΛΖΛΤΊî°bΛρΕ…ΛΖΛΤΛδΛξΛΩΛΛΛ»ΛΔΛιΛφΛκ ÷ΛρΛΡΛ·ΛΖΛΒΛ§ΛΖΛΩΛ§ΛόΛκΛ«ΛφΛ·Λ®Λ§ΛοΛΪΛιΛ ΛΛΓΘΛΫΛΈΛΠΛΝΛΥΓΔΒά÷°÷ζΛΈΡΗ”HΛ§ΥάΛσΛάΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛάΛ±ΛœΓΔοLΛΈΛΩΛηΛξΛΥΛοΛΪΛΟΛΩΛ§ΓΔΉ”Λ…ΛβΛœΛ“Λ»ΛΈ ÷ΛΪΛιΛ“Λ»ΛΈ ÷ΛΊΛ»Ε…ΛΟΛΤΛΛΛΟΛΤΓΔΛΡΛΛΛ≠ΛγΛΠΛΈ»’ΛόΛ«ΛφΛ·Λ®Λ§ΛοΛΪΛιΛ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΗΛΣΛ»ΛΠΛΒΛσΛœ¦QΛΖΛΤΓΔΛœΛΗΛαΛΪΛιΛΫΛσΛ êôΛΛΛ≥Λ»ΛρΛΩΛ·ΛιΛσΛάΛοΛ±ΛΗΛψΛ ΛΛΓΘΛΖΛΪΛΖΫYΙϊΛΪΛι“äΛκΛ»ΓΔΛΛΛόΛόΛ«Βά÷°÷ζΛΈΊî°bΛρΉ‘Ζ÷ΛΈΛβΛΈΛΥΛΖΛΤΛΛΛΩΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛκΓΘΛΣΛ»ΛΠΛΒΛσΛœΛΫΛλΛρΛ…ΛσΛ ΛΥΩύΛΥΛΖΛΤΛΛΛΩΛμΛΠΓΘΛάΛΪΛιΛΛΛΟΛ≥Λ·Λβ‘γΛ·Βά÷°÷ζΛρΛΒΛ§ΛΖΛάΛΖΛΤΓΔΛύΛΪΛΖΛΈΉοΛέΛμΛήΛΖΛΥΓΔΛΔΛ»ΛΡΛ°ΛΥΛΖΛΤΊî°bΛρΛφΛΚΛξΛΩΛΛΛ»ΥΦΛΟΛΤΛΛΛΩΛΈΛάΛ§ΓΔΛβΛΠΛΛΛ±Λ ΛΛΓΘΛάΛαΛάΓΘΒά÷°÷ζΛœ άΛΥΛβΩ÷ΛμΛΖΛΛΛ…Λ·ΛμΘέΘΘΓΗΛ…Λ·ΛμΓΙΛΥΑχΒψΘί÷ΗΦyΛΈΙ÷ΒΝΛ ΛΈΛάΓΙ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓχQΛξΛδΛύΗηïr”΄
ΓΓΛœΛΗΛαΛΤ¬³Λ·ΗΗΛΈΟΊΟήΛΥΓΔΟάΖΘßΉ”ΛœΛ…ΛσΛ ΛΥΛΣΛ…ΛμΛΛΛΩΛμΛΠΓΘ
ΓΓ®D®DΛΔΛΔöίΛΈΛ…Λ·Λ ΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΓΘΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΛ§êôΛΛΛΈΛΗΛψΛ ΛΛΛοΓΘΛΏΛσΛ ΛΫΛΈΡΗ”HΛ»ΛΛΛΠΛ“Λ»Λ§êôΛΛΛΈΛάΛοΓΘ
ΓΓΛ»ΓΔΛΫΛΠΥΦΛΠΛΖΛΩΛΪΛιΓΔΛόΛΩΒά÷°÷ζΛΈΛ≥Λ»ΛρΩΦΛ®ΛκΛ»ΓΔΞΨΞΟΛ»ΛΙΛκΛηΛΠΛ Ω÷ΛμΛΖΛΒΛ§Λ≥ΛΏΛΔΛ≤ΛΤΛ·ΛκΓΘ
ΓΓ®D®DΛβΛΖΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΛ§ΛΫΛΈΛ»Λ≠ΓΔΛΙΛ ΛΣΛΥΊî°bΛρΕ…ΛΖΛΤΛΣΛΛΛΩΛιΓΔΛΔΛΈΛ“Λ»ΛβΩ÷ΛμΛΖΛΛΛ…ΛμΛήΛΠΛ Λ…ΛΥΛ ΛιΛΚΛΥΛΙΛσΛάΛΪΛβ÷ΣΛλΛ ΛΛΓΘ άΛΈΛ ΛΪΛΥΛœΓΔΛΖΛσΛΜΛΡΛ«ΛΖΛΩΛ≥Λ»Λ«ΛβΓΔΥΦΛΛΛ§Λ±Λ ΛΛêôΛΛΛ≥Λ»ΛρΛ“Λ≠ΤπΛ≥ΛΙΛ≥Λ»ΛβΛΔΛκΓΘΛβΛΖΒά÷°÷ζΛ§ΛΫΛλΛρ÷ΣΛΟΛΩΛιΓΔΛ…ΛσΛ ΛΥΗΗΛρΛΠΛιΛύΛάΛμΛΠΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛρΩΦΛ®ΛκΛ»ΟάΖΘßΉ”ΛœΛ ΛσΛ»ΛβΛΛΛ®ΛΚ≤ΜΑ≤ΛΥΛ ΛκΓΘΛ’ΛΖΛ°Λ ΏΟϋΛΈΛΛΛΩΛΚΛιΛΥΓΔ±Υ≈°ΛœΛΫΛΈ»’ΛΛΛΝΛΥΛΝΤϋΛ≠ΡΚΛιΛΖΛΩΛ§ΓΔΛΒΛΤΓΔΛΫΛΈ“ΙΛΈΛ≥Λ»®D®DΓΘ
ΓΓΤϋΛ≠ΛΧΛλΛΤ«ό»κΛΟΛΤΛΛΛΩΟάΖΘßΉ”ΛœΓΔ’φ“Ι÷–Λ¥ΛμâτΛΈΛ ΛΪΛ«ΓΔΛΩΛάΛ ΛιΛΧ±·χQΛρ¬³ΛΛΛΩΛηΛΠΛ öίΛ§ΛΖΛΤΓΔΞœΞΟΛ»ΡΩΛ§ΛΒΛαΛΩΓΘ
ΓΗΛΔΛιΓΔΛΔΛλΓΔΛ ΛσΛΈ…υΛάΛΟΛΩΛΪΛΖΛιΘΩΓΙ
ΓΓ–ΊΛρΞ…Ξ≠Ξ…Ξ≠ΛΒΛΜΛ Λ§ΛιΓΔΛΗΛΟΛ»¬³Λ≠ΕζΛρΛΩΛΤΛΤΛΛΛκΛ»ΓΔΛ…Λ≥ΛΪΛ«ΛΪΛΙΛΪΛ ΞΣΞκΞ¥©Γ°ΞκΛΈ“τΛ§ΛΙΛκΓΘΞΣΞκΞ¥©Γ°ΞκΛœ”ξΛάΛλΛΈ“τΛΈΛηΛΠΛΥΓΚΆwΛΈΙβΓΜΛΈΞαΞμΞ«ΞΘ©Γ°ΛρΘϋΉύΓΕΛΪΛ ΓΖΛ«ΛΤΛΛΛκΓΘΟάΖΘßΉ”ΛœΞœΞΟΛ»ΛΖΛΤ’μΛβΛ»ΛΈïr”΄Λρ“äΛκΛ»ΓΔΛΝΛγΛΠΛ…»ΐïrΛάΓΘ
ΓΗΛόΛΔΓΔΛΫΛλΛΗΛψΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΓΔΫώ“ΙΛβΛΣ Υ ¬ΛΪΛΖΛιΘΩΓΙ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛΣΛβΛοΛΚ ΉΛρΛΪΛΖΛ≤ΛΩΓΘ
ΓΓΉΎœώ≤© ΩΛœΛηΛ·’φ“Ι÷–ΛΥΤπΛ≠ΛΤ Υ ¬ΛρΛΙΛκΛ≥Λ»Λ§ΛΔΛκΓΘΛΫΛσΛ Λ»Λ≠ΓΔ≤© ΩΛœΛΛΛΡΛβΓΔΡΩΛΕΛόΛΖïr”΄ΛρΛΪΛ±ΛΤΛΣΛ·ΛΈΛάΛ§ΓΔΛΫΛΈΡΩΛΕΛόΛΖïr”΄Λ»ΛΛΛΠΛΈΛœΗηïr”΄ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛΤΓΔΞΌΞκΛΈΛΪΛοΛξΛΥΞΣΞκΞ¥©Γ°ΞκΛ§ΓΚΆwΛΈΙβΓΜΛρΉύΛ«ΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΛΈΛάΓΘ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛάΛΪΛιΓΔ’φ“Ι÷–Λ¥ΛμΛΫΛΈΞΣΞκΞ¥©Γ°ΞκΛ§χQΛξ≥ωΛΙΛ»ΓΔΛΛΛΡΛβΓΔΛΔΛΔΓΔΛόΛΩΫώ“ΙΛβΛΣ Υ ¬ΛάΛοΓΔΛ»ΛΫΛΈΛόΛό«όΛΤΛΖΛόΛΠΛΈΛάΛ§ΓΔΫώ“ΙΛ–ΛΪΛξΛœΛ…ΛΠΛΛΛΠΛβΛΈΛΪΓΔΗΗΛΈΛ≥Λ»Λ§öίΛΥΛ ΛΟΛΤΛΩΛόΛιΛ ΛΛΓΘΛΫΛλΛ«ΛΖΛ–ΛιΛ·ΛΗΛΟΛ»ΛΫΛΈ“τΛΥΕζΛρΛΙΛόΛΖΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΛΙΛκΛ»ΓΔΛ’ΛΛΛΥΞΣΞκΞ¥©Γ°ΞκΛΈ“τΛ§ΞœΞΩΛ»ΛδΛσΛάΓΘ
ΓΗΛΔΛιΘΓΓΙ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛΏΛγΛΠΛ –ΊΛΒΛοΛ°ΛρΗ–ΛΗΛΩΓΘΞΣΞκΞ¥©Γ°ΞκΛ§ΫKΛοΛξΛόΛ«ΗηΛοΛΚΛΥΓΔΛ»ΛΝΛεΛΠΛ«Ξ’©Γ°ΞΟΛ»ΛδΛσΛάΛΈΛ§Λ ΛσΛ»Λ Λ·öίΛΥΛΪΛΪΛκΓΘΛΫΛλΛΥΓΔΛΒΛΟΛ≠¬³ΛΛΛΩΓΔΛΔΛΈΛΩΛάΛ ΛιΛΧΫ–Λ”…υΓΘ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛΫΛ≥Λ«ΓΔΛ»ΛβΛΪΛ·ΓΔΗΗΛΈïχî»ΛρΛΈΛΨΛΛΛΤ“äΛηΛΠΛ»ΓΔ«ό “Λρ≥ωΛκΛ»ΓΔœ¬ΛΊΛΣΛξΛΤΛΛΛΟΛΩΓΘΛ»ΓΔΛΫΛ≥Λ«Λ–ΛΟΛΩΛξΛ»≥ωΜαΛΟΛΩΛΈΛ§ΓΔΗΗΛΈ÷ζ ÷ΛΈ÷ΨαΣ”Δ»ΐΛάΓΘ”Δ»ΐΛβΛ≥ΛΈΦ“ΛΥ«ό≤¥ΛόΛξΛΖΛΤΛΛΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΗΛΔΛιΓΔ÷ΨαΣΛΒΛσΘΓΓΙ
ΓΗΛΖΞΟΘΓΓΙ
ΓΓ”Δ»ΐΛœΩΎΛΥ÷ΗΛρΛΔΛΤΛΩΓΘΛ ΛσΛ»Λ Λ·ΛόΛΟ«ύΛ νÜΛρΛΖΛΤΛΛΛκΓΘΟάΖΘßΉ”ΛœΛΥΛοΛΪΛΥΓΔΛœΛ≤ΛΖΛΛ–ΊΛΒΛοΛ°ΛρΗ–ΛΗΛ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΛΛΛΟΛΩΛΛΓΔΛ…ΛΠΛΖΛΩΛΈΘΩΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔ…υΛρΛ’ΛκΛοΛΜΛΤΛΩΛΚΛΆΛΩΓΘ
ΓΗΛ…ΛΠΛβΛΊΛσΛ ΛΈΛ«ΛΙΓΘœ»…ζΛΈïχî»ΛΈΛέΛΠΛ«ΓΔΛΏΛγΛΠΛ Έο“τΛ§¬³Λ≥Λ®ΛΩΛΈΛ«ΛΙΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔ”Δ»ΐΛβ…υΛρΛ’ΛκΛοΛΜΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΗΛΛΛΟΛΤ“äΛόΛΖΛγΛΠΓΘΛΆΛ®ΓΔΛΛΛΟΛΤ“äΛόΛΖΛγΛΠΛηΓΙ
ΓΓΛ’ΛΩΛξΛœΛΫΛ≥Λ«ïχî»ΛΊΛœΛΛΛκΛ»ΓΔΞ―ΞΝΞΟΛ»κäöίΛΈΞΙΞΛΞΟΞΝΛρΛ“ΛΆΛΟΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΛ»ΛΩΛσΓΔΞΔΞΟΛ»Ϋ–ΛσΛ«ΑτΝΔΛΝΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘΉΎœώ≤© ΩΛ§ΛΔΛ±ΛΥ»ΨΛόΛΟΛΤΛΩΛΣΛλΛΤΛΛΛκΛΈΛάΓΘ
ΓΗΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΘΓΓΓΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΘΓΓΙ
ΓΗœ»…ζΘΓΓΓœ»…ζΘΓΓΙ
ΓΓΛ’ΛΩΛξΛœΛύΛΝΛεΛΠΛΥΛ ΛΟΛΤΉσ”“ΛΪΛιΛ»ΛξΛΙΛ§ΛΟΛΩΛ§ΓΔ≤© ΩΛœΛΙΛ«ΛΥΛ≥Λ»«–ΛλΛΤΛΛΛκΓΘ“äΛκΛ»–ΊΛΈΛΔΛΩΛξΛΥΕΰΓΔ»ΐΛΪΥυΓΔΛβΛΈΛΙΛ¥ΛΛΆΜΛ≠²ϊΛρΛΠΛ±ΛΤΛΛΛκΛΈΛάΓΘ
ΓΗΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΓΔΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΓΘΛΔΛΔΓΔΛάΛλΛ§Λ≥ΛσΛ Λ≥Λ»ΛρΛΖΛΩΛσΛ«ΛΙΛΈΓΘΛΣΛ»ΛΠΛΒΛόΞΓΘΓΓΙ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛ≠ΛΝΛ§ΛΛΛΈΛηΛΠΛΥΤϋΛ≠Ϋ–ΛσΛάΛ§ΓΔΛΫΛΈΛ»Λ≠ΛάΓΔΛ ΛΥΛρ“äΛΡΛ±ΛΩΛΈΛΪ”Δ»ΐΛ§ΓΔΞΔΞΟΛ»Ϋ–ΛσΛ«ΝΔΛΝΛΔΛ§ΛκΛ»ΓΔ
ΓΗΟάΖΘßΉ”ΛΒΛσΓΔΛ¥ΛιΛσΛ ΛΒΛΛΓΘΛ≥ΓΔΛ≥ΛλΛρΘΓΓΙ
ΓΓΛ»ΛΩΛάΛ ΛιΛΧΛΒΛ±Λ”…υΓΔΞœΞΟΛ»ΛΖΛΩΟάΖΘßΉ”Λ§ΓΔ”Δ»ΐΛΈ÷ΗΛΒΛΙΛ»Λ≥ΛμΛρ“äΛκΛ»ΓΔΛΔΛΔΓΔΛ ΛσΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛάΓΔ±ΎΛΥΛΪΛΪΛΟΛΩγRΛΈ…œΛΥΓΔΞΌΞΟΞΩΞξΛ»―Σ»ΨΛαΛΈ÷ΗΦyΓΔΛΖΛΪΛβΛΫΛλΛœΛόΛ°ΛλΛβΛ Λ·ΓΔΛΔΛΈΛΛΛόΛοΛΖΛΛΛ…Λ·ΛμΘέΘΘΓΗΛ…Λ·ΛμΓΙΛΥΑχΒψΘί÷ΗΦyΛ«ΛœΛ ΛΛΛΪΓΘ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΩ÷ΛμΛΖΛΛ’φœύ
ΓΓΟςΛ±ΖΫΛΈΈεïrΛ¥ΛμΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ–¬»’àσ…γΛΈ»ΐΫρΡΨΩΓ÷ζΛœΓΔ”…άϊœ»…ζΛΥΛΩΛΩΛ≠ΤπΛ≥ΛΒΛλΛΤΛΔΛοΛΤΛΤ±μΛΊΛ»Λ”≥ωΛΖΛΩΓΘ“äΛκΛ»”…άϊœ»…ζΛœΉ‘³”ή΅ΛΥΛΈΛΟΛΤ¥ΐΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΗ»ΐΫρΡΨΨΐΓΔΛΛΛΟΛΖΛγΛΥΛΛΛ≥ΛΠΓΘΛ…Λ·ΛμΘέΘΘΓΗΛ…Λ·ΛμΓΙΛΥΑχΒψΘί÷ΗΦyΛ§»ΥöΔΛΖΛρΛδΛΟΛΩΛ»ΛΛΛΠΛΈΛάΛηΓΙ
ΓΗΛ®ΓΔ»ΥöΔΛΖΛ«ΛΙΛΟΛΤΘΩΓΓΛΫΛΖΛΤΓΔöΔΛΒΛλΛΩΛΈΛœΛΛΛΟΛΩΛΛΛάΛλΛ«ΛΙΘΩΓΙ
ΓΗΉΎœώ≤© ΩΛάΛηΓΙ
ΓΗΛ ΛΥΉΎœώ≤© ΩΛ«ΛΙΛΟΛΤΘΩΓΙ
ΓΗΛΫΛΠΛάΓΔΛΛΛόΨ·“ïéΊΛΈΒ»Γ©ΝΠΨ·≤ΩΛΪΛι÷ΣΛιΛΜΛΤΛ≠ΛΩΛσΛάΓΘΛ»ΛβΛΪΛ·Λ≠ΛΩΛόΛ®ΓΙ
ΓΓ”…άϊœ»…ζΛΥΛΠΛ Λ§ΛΒΛλΛΤΓΔΩΓ÷ζΛ§Ή‘³”ή΅ΛΥοwΛ”¹ΛκΛ»ΓΔΥΦΛΛΛ§Λ±Λ Λ·ΓΔœ»…ζΛΈΛΫΛ–ΛΥΛœ“ä÷ΣΛιΛΧ»τΛΛΡ–Λ§ΛΈΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΛΫΛΈΡ–Λœ¥σΛ≠Λ ϋ―έγRΛρΛΪΛ±ΓΔΟ±Ή”ΛρΛόΛ÷ΛΪΛΥΛΪΛ÷ΛξΓΔΛΣΛόΛ±ΛΥΞ≥©Γ°Ξ»ΛΈΛ®ΛξΛρΛ’ΛΪΛ÷ΛΪΛ»ΝΔΛΤΛΤΛΛΛκΛΈΛ«ΓΔ»ΥœύΛœΛόΛκΛ«ΛοΛΪΛιΛ ΛΛΓΘ”…άϊœ»…ζΛβΛΖΛγΛΠΛΪΛΛΛΖΛηΛΠΛ»ΛœΛΖΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΓΗΛΫΛλΛ«œ»…ζΓΔ ¬ΦΰΛΈΤπΛ≥ΛΟΛΩΛΈΛœΛΛΛΡΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΙΓΙ
ΓΗΛΡΛΛΛΒΛ≠ΛέΛ…ΓΔ»ΐïrΛ¥ΛμΛΈΛ≥Λ»ΛάΛΫΛΠΛάΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛΫΛσΛ Λ≥Λ»ΛρΛΛΛΟΛΤΛΛΛκΛΠΛΝΛΥΓΔΉ‘³”ή΅Λœ‘γΛ·ΛβΦoΈ≤Ψ°ν°ΛΈΉΎœώέΓΛΊΛΡΛ·ΓΘ“äΛκΛ»ΈίΖσΛΈ÷ή΅λΛΥΛœΓΔΛœΛδâδ ¬ΛρΛ≠Λ≠ΛΡΛ±ΛΩΛδΛΗΛΠΛόΛ§ΛΣΛΣΛΦΛΛΛύΛιΛ§ΛΟΛΤΛΛΛΤΓΔΛΫΛΈΛ ΛΪΛΥΓΔ÷ΤΖΰΛΈΨ·ΙΌΛδΥΫΖΰΛΈ–Χ ¬ΛΈΛΙΛ§ΛΩΛβ“äΛιΛλΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΛ ΛΪΛρΛΪΛ≠ΛοΛ±ΛΤ”…άϊœ»…ζΛΥΓΔ»ΐΫρΡΨΩΓ÷ζΓΔΛΫΛλΛΪΛιάΐΛΈϋ―έγRΛΈΡ–ΛΈ»ΐ»ΥΛ§Λ ΛΪΛΊΛœΛΛΛΟΛΤΛΛΛ·Λ»ΓΔ≥ω”≠Λ®ΛΩΛΈΛœΒ»Γ©ΝΠΨ·≤ΩΛάΓΘ
ΓΗΛδΛΔΓΔœ»…ζΓΘΛηΛ·Λ≠ΛΤΛ·ΛλΛόΛΖΛΩΛΆΓΙ
ΓΗΛ’ΛύΓΘœ»≥ΧΛœκä‘£ΛρΛΔΛξΛ§Λ»ΛΠΓΘΛ»Λ≥ΛμΛ«ΛόΛΩΛ…Λ·ΛμΘέΘΘΓΗΛ…Λ·ΛμΓΙΛΥΑχΒψΘί÷ΗΦyΛ§≤–ΛΟΛΤΛΛΛΩΛΫΛΠΛάΛΆΓΙ
ΓΗΛΫΛΠΛ«ΛΙΛηΓΘΛΗΛΡΛΥΛ’ΛΖΛ°Λ«ΛΙΛηΓΘΛ»Λ≠ΛΥœ»…ζΓ≠Γ≠ΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΨ·≤ΩΛ§Λ ΛΥΛΪΛΒΛΒΛδΛ·Λ»ΓΔ”…άϊœ»…ζΛœΞΥΞσΞόΞξΛΠΛ ΛΚΛ≠Λ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΛΛΛδΓΔΛάΛΛΛΗΛγΛΠΛ÷ΛάΓΘΛΫΛλΛœΛοΛΖΛ§±Θ‘^ΛΙΛκΓΘΛφΛΠΛΌΛœΛΚΛΟΛ»ΛοΛΖΛΈΛΫΛ–ΛΥΛΛΛΩΛΈΛάΛΪΛιΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛΏΛγΛΠΛ Λ≥Λ»ΛρΛΛΛΟΛΩΛΪΛ»ΥΦΛΠΛ»ΓΔ
ΓΗΛ»ΛΥΛΪΛ·ΓΔ§FàωΛρ“äΛΜΛΤΛβΛιΛΣΛΠΛΪΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΩΓ÷ζΛ»ϋ―έγRΛΈΡ–ΛρΛΠΛ Λ§ΛΖΛ Λ§ΛιΓΔïχî»ΛΊΛœΛΛΛΟΛΤΛΛΛΟΛΩΓΘïχî»ΛœΛόΛάΛΒΛΟΛ≠ΛΈΛόΛόΛ«ΓΔΉΎœώ≤© ΩΛΈΥάΧεΛβΛΫΛ≥ΛΥΚαΛΩΛοΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΗœ»…ζΓΔΛ≥ΛλΛ§άΐΛΈ÷ΗΦyΛ«ΛΙΓΘΛΫΛΖΛΤΓΔΛ≥ΛΈ–¥’φΛ§ΓΔΛφΛΠΛΌ»ΐΫρΡΨΨΐΛ§ΞΝΞιΛ»–ΓΕζΛΥΛœΛΒΛσΛάΛ»ΛΛΛΠ–¥’φΛΥΛΝΛ§ΛΛΛΔΛξΛόΛΜΛσΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔȎΝΠΨ·≤ΩΛ§÷ΗΛΒΛΖΛΩΛΈΛœΓΔάΐΛΈάθ…ζèΊ‘’ΛΈ–¥’φΛάΓΘΛΫΛλΛρ“äΛκΛ»ΓΔ”…άϊœ»…ζΛβΩΓ÷ζΛβΞΔΞΟΛ»Λ–ΛΪΛξΛΥΛΣΛ…ΛμΛΛΛΩΛ§ΓΔΛ»ΛξΛοΛ±ΛΛΛΝΛ–ΛσΛΣΛ…ΛμΛΛΛΩΛΈΛœϋ―έγRΛΈΡ–ΓΘΛόΛκΛ«”ΡκëΛ«Λβ“äΛΡΛ±ΛΩΛηΛΠΛΥΓΔΛΗΛΟΛ»ΛΫΛΈ–¥’φΛΈ«ΑΛΥΝΔΛΝΛΙΛ·ΛσΛ«ΛΛΛΩΛ§ΓΔ”…άϊœ»…ζΛ§ΞίΞσΛ»ΛΫΛΈΦγΛρΛΩΛΩΛ·Λ»ΓΔ
ΓΗΛηΛΖΛηΛΖΓΔΛΛΛόΛΥΚΈΛβΛΪΛβΫβ¦QΛΙΛκΓΘ–Ρ≈δΛΙΛκΛ ΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛόΛΩΛΖΛΤΛβΛΏΛγΛΠΛ Λ≥Λ»ΛρΛΛΛΠΛ»ΓΔ
ΓΗΛΫΛλΛΗΛψΨ·≤ΩΓΔΑk“ä’ΏΛάΛ»ΛΛΛΠΛΣ΄ίΛΒΛσΛρΚτΛσΛ«Λ·ΛλΛΩΛόΛ®ΓΙ
ΓΓΛδΛ§ΛΤΓΔΨ·≤ΩΛΈΟϋΝνΛΥΛηΛΟΛΤΛœΛΛΛΟΛΤΛ≠ΛΩΛΈΛœΟάΖΘßΉ”Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛΔΛόΛξΛΈΛΪΛ ΛΖΛΏΛΥΓΔΛΙΛΟΛΪΛξνÜ«ύΛΕΛαΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΛΫΛλΛ«Λβ”…άϊœ»…ζΛΈΌΘϋÜ•ΛΥΛΩΛΛΛΖΛΤΓΔΛφΛΠΛΌΛΈ‘£ΛρΞίΞΡΞίΞΡΛ»‘£ΛΖΛΤΛ≠ΛΪΛΜΛΩΓΘ”…άϊœ»…ζΛœüα–ΡΛΥΛΫΛΈ‘£Λρ¬³ΛΛΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΗηïr”΄ΛΈΞΣΞκΞ¥©Γ°ΞκΛ§Λ»ΛΡΛΦΛσχQΛξΛδΛσΛάΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»Λρ¬³Λ·Λ»ΓΔΛ’ΛΖΛ°ΛΫΛΠΛΥΓΔ
ΓΗΛΫΛΈΗηïr”΄Λ»ΛΛΛΠΛΈΛœΛ≥ΛλΛ«ΛΙΛΪΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛφΛΪΛΈ…œΛΥΛ≥ΛμΛ§ΛΟΛΤΛΛΛκΡΩΛΕΛόΛΖïr”΄ΛρΛ»ΛξΛΔΛ≤ΛΩΓΘ
ΓΗΛœΛΛΓΔΛΫΛλΛ«Λ¥ΛΕΛΛΛόΛΙΓΙ
ΓΗΛ ΛκΛέΛ…ΓΔΛ≥ΛλΛ§Λ»ΛΝΛεΛΠΛ«χQΛξΛδΛσΛάΛΈΛ«ΛΙΛΆΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛΖΛ≤ΛΖΛ≤ïr”΄ΛρΛ Λ§ΛαΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΛδΛ§ΛΤΞ°ΞγΞΟΛ»ΛΖΛΩΛηΛΠΛ ±μ«ιΛρΛΔΛοΛΤΛΤ―ΚΛΖΛΪΛ·ΛΖΛ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΛ»Λ≠ΛΥΓΔΛΣ΄ίΛΒΛσΓΘΛ≥Λ≥ΛΥΛΪΛΪΛΟΛΤΛΛΛκΛ≥ΛΈ–¥’φΛœΓΔΛ…ΛΠΛΛΛΠΛ“Λ»Λ«ΛΙΛΪΓΙ
ΓΓΛ»¬³ΛΪΛλΛΤΓΔΟάΖΘßΉ”ΛœΞοΞΟΛ»ΤϋΛ≠≥ωΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΛΛΛόΛ»Λ ΛΟΛΤΛœκLΛΖΛηΛΠΛ§Λ ΛΛΓΘΛΫΛ≥Λ«Λ≠ΛΈΛΠΗΗΛΪΛιΛ≠ΛΛΛΩ‘£ΛρΓΔ≤–ΛιΛΚ¥ρΛΝΟςΛ±ΛΩΛ§ΓΔΛΫΛλΛρ¬³ΛΛΛΤΛΛΛΝΛ–ΛσΛΣΛ…ΛμΛΛΛΩΛΈΛœΓΔΛόΛΩΛΖΛΤΛβΛΔΛΈϋ―έγRΛΈΡ–ΛάΓΘΛΣΛβΛοΛΚΛ ΛΥΛΪΛΛΛΣΛΠΛ»ΛΙΛκΛΈΛρΓΔ”…άϊœ»…ζΛœΛΔΛοΛΤΛΤ―ΚΛΖΛ»ΛαΛ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΛΛΛδΓΔΛηΛΖΛηΛΖΓΘΛΫΛλΛ«Λœ÷ΨαΣΛ·ΛσΛ»ΛΛΛΠΛΈΛρΓΔΛ≥Λ≥ΛΊΚτΛσΛ«ΛβΛιΛΣΛΠΛΪΓΙ
ΓΓΛδΛ§ΛΤ÷ΨαΣ”Δ»ΐΛ§ΛœΛΛΛΟΛΤΛ≠ΛΩΓΘΛΪΛλΛœΛόΛάΞ―ΞΗΞψΞόΛΈΛόΛόΛ«Λ≥ΛΠΛ’ΛσΛΖΛΩνÜ…ΪΛρΛΖΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔÜ•ΛοΛλΛκΛόΛόΛΥΛφΛΠΛΌΛΈ‘£ΛρΛΙΛκΓΘ
ΓΗΛ ΛκΛέΛ…ΓΔΛΙΛκΛ»Λ≠ΛΏΛΈΩΦΛ®Λ«ΛœΓΔ≤© ΩΛρöΔΛΖΛΩΛΈΛœΒά÷°÷ζΛΥΛΝΛ§ΛΛΛ ΛΛΛ»ΛΛΛΠΛσΛάΛΆΓΙ
ΓΗΛύΛμΛσΛ«ΛΙΓΘΛΫΛΈ÷ΗΦyΛ§Λ ΛΥΛηΛξΛΈΛΖΛγΛΠΛ≥Λ«ΛΙΓΙ
ΓΗΛ»Λ≥ΛμΛ§ΛΆΓΔ÷ΨαΣΛ·ΛσΓΘΒά÷°÷ζΛœΛφΛΠΛΌΛ≥Λ≥ΛΊΛ·ΛκΛœΛΚΛœΛ ΛΛΛσΛάΓΘΛ ΛΦΛ ΛιΛ–ΓΔΛΔΛΈ…ΌΡξΛœΛφΛΠΛΌΛΚΛΟΛ»ΓΔΛ≥ΛΈΛοΛΖΛ»ΛΛΛΟΛΖΛγΛΥΛΛΛΩΛσΛάΛΪΛιΛΆΓΙ
ΓΗΛ ΓΔΛ ΛσΛ«ΛΙΛΟΛΤΘΩΓΙ
ΓΗΛΣΛΛΛ≠ΛΏΓΘΛΫΛΈ―έγRΛρΛ»ΛΟΛΤνÜΛρ“äΛΜΛΤΛδΛξΛΩΛόΛ®ΓΙ
ΓΓ”…άϊœ»…ζΛΈΛ≥Λ»Λ–ΛβΫKΛοΛιΛΧΛΠΛΝΛΥΓΔϋ―έγRΛΈΙ÷»ΥΈοΛœΓΔΞΒΞΟΛ»―έγRΛ»Ο±Ή”ΛρΛΪΛ ΛΑΛξΛΙΛΤΛΩΛ§ΓΔΛ»ΛΩΛσΛΥΟάΖΘßΉ”Λβ”Δ»ΐΛβΩΓ÷ζΛβΓΔΞΔΞΟΛ»Λ–ΛΪΛξΛΥΛΣΛ…ΛμΛΛΛΩΓΘΛύΛξΛβΛ ΛΛΓΔΛΫΛΈΡ–Λ≥ΛΫΞ©ðΞΪΞΙΛΈ»Υöί’ΏΓΔάθ…ζΒά÷°÷ζ…ΌΡξΛ«ΛœΛ ΛΛΛΪΓΘ
ΓΗΛΔΛΔΓΔΛΔΛ ΛΩΛœ®D®DΓΙ
ΓΓΟάΖΘßΉ”ΛœΛΔΛόΛξΛΈΛΣΛ…ΛμΛ≠ΛΥΓΔΛΣΛβΛοΛΚΛΠΛΖΛμΛΥΛ»Λ”ΛΒΛ§ΛκΓΘ”Δ»ΐΛβΛόΛΟ«ύΛΥΛ ΛΟΛΤΛΩΛΗΛμΛΛΛάΓΘ
ΓΗΛΣ΄ίΛΒΛσΓΔΑ≤–ΡΛ ΛΒΛΛΓΘΒά÷°÷ζΛ·ΛσΛœΛ±ΛΟΛΖΛΤêôΒ≥ΛΗΛψΛ ΛΛΓΘΛ ΛκΛέΛ…ΤφΙ÷Λ ÷ΗΦyΛΈ≥÷ΛΝ÷ςΛάΛ§ΓΔΛΫΛΈ÷ΗΦyΛρΛΧΛΙΛσΛ«êô ¬ΛρÉPΛΛΛΤΛΛΛΩΛδΛΡΛœ³eΛΥ