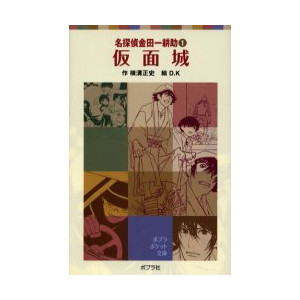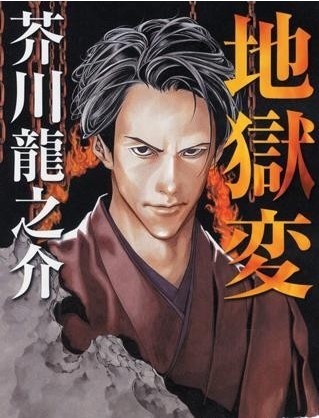�����(����)-��22��
�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������
��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���
������о����Ϥ��I���ʤ��ơ�������������Ǥ��ĤǤ�ˤ������ݤΤɤ�����˼�äƤ��ޤ���
���ʤ�ۤɡ��褯�狼��ޤ���������Ǥ��ߤϡ��������ƤϤ��餤�ơ��ˤ�������о��������Ƥ���ΤǤ��͡�
���������������Ф��ޤ��������Ƥ���ä����С�����ʤ��Ȥ����Ȥ�褫�ä��ΤǤ�����ɡ�����
�����Ф��ޤȤ����ȡ�����
����������ޤ�����ȥ�ꥦ�������������ʤä����S�ҤΣ��R�����桷���������������ȡ����ӡ������Ȥ����ҤȤǤ��Ρ�
�������ϤӤä��ꤷ�������Ӥ��Ҋ����
���ձ��ˤ��R�����Ӥ�����֪����ߤ���������������ձ��Τۤ���ۣ����ۤ���˰���ݤȤ������⡢����α���ȤޤǤ�������줿�������ܿ�g�ҤǤ��롣
�������R�����Ӥ������Τޤ������ѥ��ݤΉӤ��ӤΤ��ФǤ������Ȥϣ�
�����ФϤ䤵���������Ǥ���������������һ�Ҥˡ��Ĥ��Ĥ��Ȳ��Ҥ��𤳤ä��Ȥ��ˤϡ����Τ������h������ˤ���줿�ΤǤ��������Τ����������ۤ�Ȥ��ˡ��������������äΤ���������Ƥ��������ޤ�����
�������ơ��ˤ������ΰk���˟��Ф������Ƥ���Ȥ�����Ρ�����֤����H�ݤ��������Ĥ��Ĥ��ȤϤʤ�Ƥ��ä��ʤ��ˡ����Ф����Ϥ��Ĥ��������䤵���������줤���ּ��������ޤ�����
���о����M�äˤȤ��äơ��Ф������ʤ�����ͤäƤ������ä����Ȥ�һ�Ȥ���ȤǤϤ���ޤ������������Τ��Ф��Ϥ⤦���ʤ��ҤȤǤ���
�������������Ф��ޤ����ʤ��Ȥ������ߤ����ˤϡ��ʤˤ�Ф��Ƥ����ʤ��ä��Ρ�
�����Фϡ�����Τ��ȤˤϤ����äƵ��פʤ����Ǥ����Ρ������餪�����ʤ�ˤʤä����ȡ������鷺����ؔ�b�����ФäƤ��ʤ��ä��Ȥ���Ԓ�Ǥ��������ߤ�ʡ��H�ݤΤҤȤ������櫓�Ƥ��ޤäơ������������ˤϡ��ʤˤҤȤĤ椺���ޤ���Ǥ������ʤˤ������Ф��ޤ⡢����ʤˤ��夦�����̤ȤϤ�˼���ˤʤ�ʤ��ä��Τǡ������������Τ���ˡ�����Ƥ����Ƥ�������Ҥޤ��ʤ��ä��ΤǤ��
�������Ӥϡ��ۥäȤ��뤤����Ϣ���餷����
�����Ϥ��Ĥ����Ϥ���ơ�����ɭ�Τʤ��ˤ��������äƤ��������Τ������ɭ�ϡ����iҰ�Ǥ������ʤΤ������������ȤΤӤ������δ�ľ������Ǥ⡢���ä����Ȥ����դι�����äƤ��롣�ޤ��Ƥ䤳��ҹ�դ���ͨ�ꤹ����ΤҤȤʤɤ������Ϥ����ʤ��ä���������äȣ��ҡ�����������椹�֤��L�Τ�Τ���������һ�ᩡ��ȥ��Ȥ�Ҋ���ʤ��ޤð�霤Κ�ζ������
�����顢�����ʤ������Ĥޤ�ʤ�Ԓ�˚ݤ�Ȥ��Ƥ�����h���ޤ��ͤäƤ����������ꤷ�ơ��⤦���������Ǥ��Ρ��ۤ顢�ळ���ˣ��ơ������꡷�ΤĤ����Ҥ�Ҋ����Ǥ��礦�����줬���������μҤǤ��Ρ��ɤ���������ˤʤäơ�
���Ĥ��Ǥ����顢�Ҥ�ǰ�ޤ��ͤ�ޤ��礦��
�����������⤦���ɤ����ɤ�������������⤦�Ҥ��ߤ�Ǥ���܇���ʤ��ʤ�Ȥ����ޤ��ۤ�Ȥ��ˤ⤦��������ʤ��äơ�
�������Ӥ�����ޤꤤ����Τ����顢�����ƤȤ����Τ⤫���äƐ�������˼�ä��������ǿ�����ñ�Ӥ��֤Ƥ�ȡ�
�������Ǥ��������㤢����Ǥ��Ĥ줤���ޤ��礦��
�����꤬�Ȥ��������ޤ�����
�������������Ȥ��Ӥ��ۣ������Ӥ����˰���ݤ������Ȥ����L��������äȤ�����ޤ��ơ��դ�����܇��ͨ�ꤹ���Ƥ��ä���
����������霤Υԥ���
�����Ȥ��鿼����ȡ����ΤȤ������ϡ���äѤ�Ҥ�ǰ�ޤ������Ӥ��ͤäƤ��äƤ�ä��ۤ����褫�ä��ΤǤ��롣�Ȥ����Τϡ����줫���g��ʤ����Ĥ��Τ褦�ʿ֤������¼����������Ӥ����ˤդ꤫���äƤ����������
�������˄e�줿�ص㤫�������ӤμҤޤǡ������褦��Ҋ���ơ����Τ��Ĥ��ʤ�ξ��x�����ä��������Ӥϥޥե驡��Τޤ����Ϥ碌�ơ����Ĥभ�������һ�Ĥ����Ϥ��Ф�����
�������ӤϤ�äȰ���ɭ��Ĥ��̤��ơ������������֤��Ϥˤ��������ä������Τؤ�ϡ��Ǥ�����Ǥ����餫��������Ҋ����Τ��������ӤμҤϤĤ���Ŀ�ȱǤ��Ȥˤ��ޤäƤ�����
���ȡ����ΤȤ��Ǥ��롣�ȤĤ����Ф��Υ����δ�ľ�θ���Ȥ��顢�椦�椦�Ȥ��ɤ�����Ƥ������ޤðפʴ�����������ӤϥϥäȤ��Ƥ��������������ࡣ
�������ΤǤ褯�狼��ʤ������פ�������Ť����ȤƤⱳ�θߤ����g�Ǥ��롣
�������Ĥ��ҥ祤�ҥ祤�Ȥ��ɤ�褦�����Ĥ��ǡ������Ӥ�ǰ�������դ�����ȡ������ʤ���֤������Ӥμ��Ĥ������
�����ݥ����ݥ����ʥ�����������Υ��ݥ��ǥ��硹
���ߤ礦���������Ǥˤ����ä����ȤƤ�դᤤ��礦�ʤ��ȤФĤ��ʤΤǤ��롣�����ӤϿ֤������Τ���ˡ�ȫ����Ѫ����������һ�r�ˤ����äƤ��ޤ��褦�ʚݤ�������
��Ҋ��Ȥ��δ�����ϡ����礦�ɥ���������ʤɤˤ褯���Ƥ��롢�ԥ����Τ褦�ʷ�װ�Ƥ���ΤǤ��롣�Ȥˤդ��ۣ����դ����˰���ݤΤĤ��������ͤΥȥ�ñ�ˡ��ؤ˳त���Ȥ����ɤ���������������֥��֤���������ޤ��ˡ����Υԥ�������֤äƤ��롣
������Τʤ����ޤðפʤ�����Κ�ζ������
�����ݥ����ݥ��勵�������ʥ���Ԓ����ޥ������磻���ȥ���ޥ���
�������ӤϿ֤������ˡ��֥�֥�դ뤨�Ƥ����������夦���ݤ�դ�äơ��ФΤ������Ĥ��Τ���ȡ�
���Ϥʤ��Ƥ����������Ϥʤ��Ƥ����������Ϥʤ��ʤ��ȡ����������Ƥޤ��衹
�����졢�������ˡ��ӥ��襦�ȥ��åƥ⡢�勵���ӥ����ޥ���
������ã������줫���Ƥ�����
�����ˤ��ɤ����ơ���֤ʥԥ����Ϥ����ʤ���֤������Ӥοڤ�դ������Ȥ��롣
����������ޤ��Ȥ��롣�������Ƥ��뤦���ˡ��ԥ������֤��դ������ӤΥޥե驡��ˤ����ä�������Ȥʤ�˼�ä������ԥ����Ϥ����ʤ�ޥե驡��ΤϤ���路�Ť��ߤˤ��������Υޥե驡��Ǥ��뤰�Ĥ�Ǥ�Ϥ�褦��˼�ä��Τ��⤷��ʤ������륺��ȿ֤��������ǥޥե驡��������Τ���
�������ӤϤ����Ȥ��ޤ��Ȥ���һ������ᤤ�����ޥե驡��������Ӥμ��Ϥ���ơ��դ���Τ������˰��Τ褦�˥ԥ�ȏ����Фä����������Ƥ��뤦���ˡ������Ӥ����դߤ��٤餷�����餿�ޤ�ʤ����ޥե驡��ΤϤ���ˤ��ä��ޤޡ����륺������֤��Ϥ��鴨�Τۤ�������Ƥ��ä���
�����֤��Ϥ˥ԥ��������ޥե驡��Τ⤦���äݤ��ΤϤ���֤ä��ޤ�����Τ褦�ˤĤ����äƤ��롣
���ϥʥ��ʥ����������֥�ϥʥ��ʥ�����
��������������Ǥ������줫���Ƥ���������
�������Ӥ�����夦�ˤʤäƽФ���Ȥ��Ǥ��롣�ळ���Τۤ����餤������Ǥ����Ĥ��Ƥ���ҤȤ�����������������������ȡ��ԥ����ϥ����ä��द����ȡ������ʤ�ݥ��åȤ���ʥ���å����ʥ��դ�ȡ������ơ����äȤ����Ĥ�դꤪ��������
�������
�������Ӥ��Ф���Ȥ��ˤϤ��Ǥˤ������ä����ޤó��ë��Υޥե驡������ޤ�ʤ�����ӥ�ӥ�Ȥ����Ф�줿����˼���ȡ��Ϥ���ˤ��ä������ӤΤ�����ϡ����ɤꤦ�ä����֤���ܞ�䤷�Ƥ��ä��ΤǤ��롣
���ԥ����Ϥ��Ф餯���Ф��ˤʤꡢ���ä��¤Τۤ������äƤ��������դ��ˤ�������𤳤��ȡ����Τ��ɤ�褦�ʲ��������ǡ��ҥ祤�ҥ祤��霤Τʤ��������Ƥ��ä����ȡ��ۤȤ��ͬ�r�ˤ��Έ��ؤ����Ĥ��Ƥ����ҤȤ���С�
�����������ʡ����������Τؤ�ǤҤȤ����������褦���ä����ʡ�
���ȡ�����늟���Ȥ�����Ƥ�������դ餷�Ƥ�����Ҋ��Ȥޤ����ʤ������Фϡ����ä��܇�Τʤ��������ӤӤ䤫���������Τ��������ޤΥ�����Ȥ�С�ФʤΤǤ��롣
���ФϤ��Ф餯����늟��ǵ�����Ϥ�գ��٤Ƥ����������Τ������դȤߤ礦�ʤ�Τ�Ҋ�Ĥ���������ϤҤȤ��㤢�ȤʤΤǤ��롣�������㤢�Ȥˤ��ƤϤߤ礦�ʤȤ��������ä����Ȥ����Τϡ������㤢�ȤȤ����ΤϤ���һ�ġ��Ҥ�ѥ���Ȥ����ʤ��Τ��������ơ��Ȥ��������ѥ���Ȥ�Ҋ���ʤ���Фʤ�̤Ȥ����ˤϡ����ƥå��Τ��ȣۣ������ȡ��˰���ݤߤ�����С���ʤ��ʣۣ������ʡ��˰���ݤ������ܥ��ܥ��ȤĤ��Ƥ���Τ����Ĥޤꡢ�����Ĥ������ˡ����Τ褦���x���Ϥ������㤢�ȤʤΤ���
�������Ҋ��ȡ�������ۣ��������˰���ݤ��Фϡ���������늟��������ơ�
�����ޤä����������ä�������
���ȽФ֤ȡ����ä����霤Τʤ��������������Τ��Ȥ��顢�����Ӥ��֤�֤�����������������夦����餱�ˤʤäơ��Ȥ����ɤ���������ۣ���������˰���݂����Ǥ��ơ���������Ѫ���ˤ���Ǥ��롣����Ǥ��Ů�Ϥޤ�����夦�ˤʤäơ��ޥե驡����Ф�Ϥ���ˤ��äƤ�����
�������ӤϤ��Ф餯霤Τʤ���Ŀ���ơ����äȤ���������äƤ��������䤬�ƥ������������֤��ϤˤϤ�������ȡ���������褦�ˤ��Ǝ��äƤ����ΤϤ郎�Ҥα��ڤ���
���ˤ����ˤ�����
���ȡ�Ϣ�����Фä����v��С��������Ҥ餤�������Ӥϡ������Ǥޤ����ϥäȤ�������������Ǥ��ޤä��ΤǤ��롣
������Τʤ��ˤ��֤ν�һ�����뤰�Ĥ��Ϥ��졢�����֤��֤ˤ��Ф��ơ�����Ƥ����ǤϤʤ�����
�����������ޥե驡����Ф�Ϥ�
���������դ�Ϧ���������Τ��Ȥ��ʤ���늤Τʤ��ǡ����I�ä��Ф����Ϧ����Ҥ餤���i��Ǥ��������ϡ��դ��˥ϥäȤ����褦���ɫ������
���k�������á��֝h�ˤ�����롹
���Ȥ����褦��Ҋ�����Τ�Ȥˡ���ҹ�������¤��𤳤ä����¼����ǥ��ǥ��ȤΤäƤ���Τ�������ˤ��Ȥ�����Σۣ���������Ρ��˰���ݤϤ������硢������һ����լ�ˤ�������������֤��֤ˤ��Фꤢ���ƼҤ��夦�����ޤ路�Ƥ��ä��Τ�������ɤ��ä������ӤΎ������������ơ�������u�Ĥ����Ȥ����ΤǤ��롣
�������ϡ�������i��Ȥޤ���ˤʤä���
���D�D�������ɤ����Ƥ��ΤȤ������֤�Ϥ��ˤǤ⡢�����Ӥ�Ҥ�ǰ�ޤ��ͤäƤ��ʤ��ä��Τ����������֤��Ĥ��Ƥ���С�����ʿ֤��������Ȥ��𤳤�Ϥ��ʤ��ä��Τ���
�����ˤϡ����ޤ꤯�路�����Ȥϳ��Ƥ��ʤ����������ӤϤҤɤ������ۣ����������˰���ݤǤ⤷���ΤǤϤʤ���������
������������ȡ����٤Ƥ�؟�Τ����֤�ˤ���褦�ʚݤ���������Ǥ��ޤ�ʤ��������ǿ����ϡ���������������������ä�Ҋ��äƤ�뤳�Ȥ˛Q�Ĥ�����
�������¤ޤ��܇���Խ���ơ���ҹ��ɭ�Τʤ���̤��Ƥ椯�ȡ�С�������֤ˤ��������ä���
���ȡ����ΤȤ����դȤߤ礦�ʤ�Τ�������Ŀ�ˤȤޤä������֤���һ��ˆD���ߤ��줿��ݤΤ������ˡ��ʤˤ��त��Τ�����Ĥ��Ƥ��롣
�����䡢�ʤ��������
�������Ϥ���鷺�����ᡢ���γत��Τ����������������ΤȤ���ϥϥäȤ����褦���ɫ��Ӥ������������Ҋ���ܤ��Τ��������ӤΥޥե驡��Ǥ��ä���������ޤ�ʤ����顢��ΤΤߤ��Ȥ˥ץåĥ�Ȥ����Ф�졢����Ǥդߤˤ��ä��褦�ˤ��äѤ��ब�Ĥ��Ƥ���ΤǤ��롣
���������������Ϥ餤��Ȥ��Ƥ���Ȥ����������Τۤ��ǡ��ݤ�դ��������������Τǡ��ϥäȤ��Ƥդ꤫����ȡ��ҤȤ���Ф���ľ���Τ����������äơ����äȤ������ʤ���Ƥ��롣
�������Ϥ����ФΤ褦����Ҋ��ȡ�����鷺�����ޤ�����
����ҹ���Ф�����ҹ��늤Τʤ��ǡ������ӤӤ䤫���������ФʤΤǤ��롣
���ФΤۤ��Ǥ⡢�������Ҋ��Ȥ���äȤ��ɤ������褦�Ǥ��ä����������˥ĥ��ĥ���ľ���Τ�����������Ƥ�����
�����ߡ����ߣ������ߤ���Ҥ��ä���ΤϤʤ���͡�
����ꤢ���ˤ����䤫�ʣ���������������͡��ʤΤǤ��롣
�������ϴ𤨤ʤ��ǡ��o�ԤΤޤޡ����ä