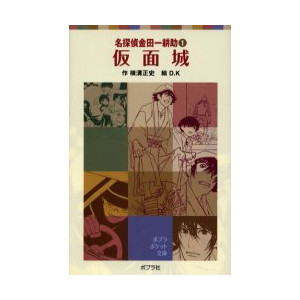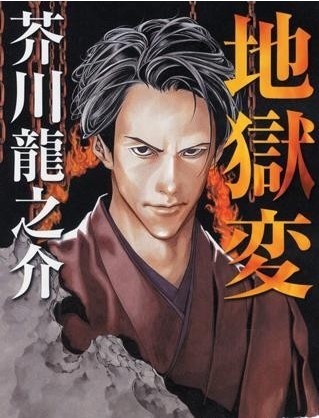¹ΔΟφ≥«(»’ΈΡΑφ)-ΒΎ19’¬
Α¥Φϋ≈Χ…œΖΫœρΦϋ Γϊ Μρ Γζ Ω…ΩλΥΌ…œœ¬Ζ≠“≥Θ§Α¥Φϋ≈Χ…œΒΡ Enter ΦϋΩ…ΜΊΒΫ±Ψ ιΡΩ¬Φ“≥Θ§Α¥Φϋ≈Χ…œΖΫœρΦϋ Γϋ Ω…ΜΊΒΫ±Ψ“≥ΕΞ≤ΩΘΓ
ΓΣΓΣΓΣΓΣΈ¥‘ΡΕΝΆξΘΩΦ”»κ ι«©“―±ψœ¬¥ΈΦΧ–χ‘ΡΕΝΘΓ
ΓΗΛόΛΔΓΔΛΣΛΥΛ°ΛδΛΪΛ«ΛΙΛ≥Λ»ΓΘΛΏΛ ΛΒΛόΓΔΛ ΛΥΛρ–ΠΛΟΛΤΛΛΛιΛΟΛΖΛψΛΛΛόΛΙΛΈΓΙ
ΓΓΛΫΛΈΛ“Λ»ΛœΘϋ…≠ΓΕΛβΛξΓΖΘϋΟάΓΕΛΏΓΖΘϋ“≤ΓΕΛδΓΖΘϋΉ”ΓΕΛ≥ΓΖΛ»ΛΛΛΟΛΤΓΔΛΣΛ ΛΗν°ΛΥΉΓΛσΛ«ΛΛΛκΡοΛάΛ§ΓΔΝΦΤΫΛΈ“ΜΦ“Λ§Λ≥ΛΝΛιΛΊΛ“ΛΟΛ≥ΛΖΛΤΛ≠ΛΤΛΪΛιΓΔ”HΛΖΛ·Λ ΛξΓΔΛΝΛΪΛ¥ΛμΛ«Λœ–ά»ΐΛΣΛΗΛΒΛσΛΈΓΔ Υ ¬ΛΈ ÷¹ΜΛΛΛρΛΖΛΤΛΛΛκΛΈΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΗΛδΛΔΓΔΟά“≤Ή”ΛΒΛσΓΔΛΛΛιΛΟΛΖΛψΛΛΓΘΛ ΛΥΛΆΓΔΝΦΤΫΛΈΛδΛΡΛ§ΓΔΛΣΛβΛΖΛμΛΛΛ≥Λ»ΛρΛΛΛΠΛβΛΈΛ«ΛΙΛΪΛιΓ≠Γ≠ΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔ–ά»ΐΛΣΛΗΛΒΛσΛ§ΛΛΛόΛΈΛΛΛ≠ΛΒΛΡΛρ‘£ΛΖΛΤ¬³ΛΪΛΙΛ»ΓΔΟά“≤Ή”ΛœΛ’Λ≠ΛάΛΙΛΪΛ»ΥΦΛΛΛΈΛέΛΪΓΔ“äΛκ“äΛκΛόΛΟ«ύΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘ
ΓΗΛόΛΔΓΔΛΫΛλΛΗΛψΛ≥ΛλΛ§ΓΔ…Φ³Ό÷°÷ζΛ»ΛΛΛΠΛ“Λ»ΛΈΫΘΐΛ ΛσΛ«ΛΙΛΈΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛΫΛΠΛΛΛΠ…υΛ§Λ ΛΦΛΪΛ’ΛκΛ®ΛΤΛΛΛκΛηΛΠΛ ΛΈΛ«ΓΔ“ΜΆ§ΛœΛΣΛβΛοΛΚνÜΛρ“äΚœΛοΛΜΛΩΓΘ
ΓΗΛΫΛΠΛ«ΛΙΛηΓΔΟά“≤Ή”ΛΒΛσΓΘΛΔΛ ΛΩΛœ…ΦΛ»ΛΛΛΠΡ–ΛρΛ¥ΛΨΛσΛΗΛ«ΛΙΛΪΓΙ
ΓΗΛœΛΔΓΔΛΔΛΈΓΔΛΝΛγΛΟΛ»Γ≠Γ≠ΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛΫΛΠΛΛΛΟΛΩΛΪΛ»ΥΦΛΠΛ»ΓΔΟά“≤Ή”ΛœΛ≠ΛεΛΠΛΥΞœΞσΞΪΞΝΛρΛάΛΖΛΤΓΔΡΩΛρ―ΚΛΒΛ®ΛΩΛΈΛ«ΓΔ–ά»ΐΛΣΛΗΛΒΛσΛβΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛβΓΔΛΛΛηΛΛΛηΛ”ΛΟΛ·ΛξΛΖΛΤΡΩΛρ“äΚœΛοΛΜΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΟά“≤Ή”ΛœΓΔΛδΛ§ΛΤ¦φΛρΛ’ΛΛΛΤΛΖΛόΛΠΛ»ΓΔ
ΓΗΛΖΛΡΛλΛΛΛΛΛΩΛΖΛόΛΖΛΩΓΘΛΡΛΛΓΔΛύΛΪΛΖΛΈΛ≥Λ»ΛρΥΦΛΛΛάΛΖΛΩΛβΛΈΛ«ΛΙΛΪΛιΓ≠Γ≠ΛοΛΩΛΖΓΔ…ΦΛΒΛσΛ»ΛΛΛΠΛΪΛΩΛΥΛΣΛΠΛιΛΏΛ§Λ¥ΛΕΛΛΛόΛΙΛΈΓΘΛ«ΛβΓΔΛΔΛΈΛΪΛΩΛρΛΣΛΠΛιΛΏΛΙΛκΛΈΛœΓΔΛοΛΩΛΖΛ…ΛβΛΈΥΦΛΛΛΝΛ§ΛΛΛΪΛβΛΖΛλΛ ΛΛΛσΛ«ΛΙΛΈΓΘΛ ΛΥΛΖΛμΓΔΛΔΛΈΛΪΛΩΛœΥάΛσΛ«ΛΖΛόΛοΛλΛΩΛΈΛ«ΓΔΛΣΛΩΛΚΛΆΛΙΛκΛοΛ±ΛΥΛβΛόΛΛΛξΛόΛΜΛσΛΖΓ≠Γ≠ΓΙ
ΓΗΟά“≤Ή”ΛΒΛσΓΔΛΫΛλΛœΛΛΛΟΛΩΛΛΛ…ΛΠΛΛΛΠΛ≥Λ»Λ«ΛΙΛΪΓΘ…ΦΛ§Λ ΛΥΛΪêôΛΛΛ≥Λ»Λ«ΛβΓΙ
ΓΗΛΫΛλΛœΛΛΛΡΛΪΓΔΛΣΛξΛ§ΛΔΛΟΛΩΛι…ξΛΖΛΔΛ≤ΛόΛΙΛοΓΘΛοΛΩΛΖΛ…ΛβΛΈΥΦΛΛΛΝΛ§ΛΛΛάΛΟΛΩΛ»ΛΖΛΩΛιΓΔ…ΦΛΒΛσΛΥΛΩΛΛΛΊΛσΛΖΛΡΛλΛΛΛ Λ≥Λ»Λ«ΛΙΛΪΛιΓ≠Γ≠ΛΫΛλΛηΛξΓΔœ»…ζΓΔΛΣ Υ ¬ΛρΛΡΛ≈Λ±ΛόΛΖΛγΛΠΓΙ
ΓΓΛΫΛλΛρ¬³Λ·Λ»ΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛœΓΔΝΦΤΫΛΈ ÷ΛρΛ»ΛΟΛΤΓΔ
ΓΗΛΫΛΠΓΔΛΫΛλΛΗΛψΝΦΤΫΓΔΛΖΛΡΛλΛΛΛΖΛόΛΖΛγΛΠΓΘΛΣΛΗΛΒΛόΛΈΛΣ Υ ¬ΛΈΛΗΛψΛόΛρΛΖΛΤΛœΛΛΛ±ΛόΛΜΛσΛΪΛιΛΆΓΘΟά“≤Ή”ΛΒΛσΓΔΛ¥ΛφΛΟΛ·ΛξΓΙ
ΓΗΛΣΛ·ΛΒΛόΓΔΛΩΛΛΛΊΛσΛΖΛΡΛλΛΛΛΛΛΩΛΖΛόΛΖΛΩΓΙ
ΓΓΟά“≤Ή”ΛœΛ ΛσΛ»Λ Λ·ΓΔΛΪΛ ΛΖΛΫΛΠΛ νÜΛρΛΖΛΤΓΔΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛδΝΦΤΫΛΥν^ΛρΛΒΛ≤ΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΆμΓΔΝΦΤΫΛœΛΗΛ÷ΛσΛΈΛΊΛδΛΊéΔΛΟΛΤΛ≠ΛΤΛβΓΔΟά“≤Ή”ΛΈΛΔΛΈΛΪΛ ΛΖΛΫΛΠΛ νÜΛ§ΓΔöίΛΥΛ ΛΟΛΤΛΩΛόΛιΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛ»ΛΛΛΠΛΈΛ§ΝΦΤΫΛœΓΔΟά“≤Ή”Λ§ΛΩΛΛΛΊΛσΛΙΛ≠Λ ΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘΟά“≤Ή”ΛœΛ»ΛΤΛβΛ≠ΛλΛΛΛ«ΓΔΛδΛΒΛΖΛ·ΛΤΓΔΛάΛλΛΥΛβΛΖΛσΛΜΛΡΛάΛΟΛΩΓΘΛΫΛΖΛΤΓΔΛ ΛΥΛρΛΒΛΜΛΤΛβΛηΛ·Λ«Λ≠ΛκΛΈΛάΓΘΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛβΛΣΛΗΛΒΛσΛβΓΔΟά“≤Ή”ΛΈν^ΛΈΛηΛΛΛΈΛρΛέΛαΛΤΛΛΛκΓΘΛΫΛλΛΥΟά“≤Ή”ΛœΓΔΛΩΛΛΛΊΛσΛ’ΛΖΛΔΛοΛΜΛ …μΛΈ…œΛ ΛΈΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΟά“≤Ή”ΛœΛύΛΪΛΖΛΪΛιΛ≥ΛΈν°ΛΥΉΓΛσΛ«ΛΛΛκΛΈΛάΛ§ΓΔΛόΛ®ΛΥΉΓΛσΛ«ΛΛΛΩΦ“ΛœΓΔΛ»ΛΤΛβΛξΛΟΛ―Λ ΓΔ¥σΛ≠Λ ΛΠΛΝΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛ§ëι’υΛΪΛιΛ≥ΛΟΛΝΓΔΛάΛσΛάΛσΛ”ΛσΛήΛΠΛΥΛ ΛξΓΔΦ“ΛβΛΤΛ–Λ ΛΒΛ Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ Λ·Λ ΛΟΛΩΛΠΛ®ΛΥΓΔΛΣΛ»ΛΠΛΒΛσΛ§Λ≠ΛεΛΠΛΥΆωΛ·Λ ΛΟΛΩΛΈΛ«ΓΔΛΛΛόΛ«ΛœΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛ»ΛΩΛΟΛΩΛ’ΛΩΛξΛ«ΓΔΛΏΛΙΛήΛιΛΖΛΛΦ“ΛΥΛΙΛσΛ«ΛΛΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ ΛΣΛΫΛΈΛΠΛ®ΛΥΓΔΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛ§ΓΔιLΛΛ≤ΓöίΛ««όΛΤΛΛΛκΛΈΛ«ΓΔΛΛΛηΛΛΛηΛ≥ΛόΛΟΛΤΟά“≤Ή”Λ§ΓΔΛœΛΩΛιΛ·ΩΎΛρ“äΛΡΛ±Λ Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ Λ·Λ ΛΟΛΩΛ§ΓΔΛΝΛγΛΠΛ…ΛΫΛΈΛ≥ΛμΓΔΛ“ΛΟΛ≥ΛΖΛΤΛ≠ΛΩΛΈΛ§ΝΦΤΫΛΈ“ΜΦ“Λ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ–ά»ΐΛΣΛΗΛΒΛσΛœΟά“≤Ή”ΛΈöίΛΈΛ…Λ·Λ ¬«ιΛρ¬³Λ·Λ»ΓΔΛΗΛ÷ΛσΛΈ Υ ¬ΛΈΓΔ ÷¹ΜΛΛΛρΛΖΛΤΛβΛιΛΠΛ≥Λ»ΛΥΛΖΛΩΓΘ
ΓΓ–ά»ΐΛΣΛΗΛΒΛσΛœ–Γ’hΦ“ΛάΛ§ΓΔ–Γ’hΛρïχΛ·ΛΩΛαΛΥΛœΓΔΛΛΛμΛΛΛμ≤ΡΝœΛρΛΔΛΡΛαΛΩΛξΓΔ’ΘϊΛΌΛΩΛξΛΖΛ Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ ΛΛΓΘΟά“≤Ή”ΛœΛΫΛΈ≤ΡΝœΛρΛΔΛΡΛαΛΩΛξΓΔΛόΛΩΓΔ΅μïχπ^ΛΊΛΛΛΟΛΤΓΔΛΛΛμΛΛΛμΛ Λ≥Λ»Λρ’ΘϊΛΌΛΩΛξΓΔ‘≠ΗεΛΈΘϋ«εΓΕΛΜΛΛΓΖΘϋïχΓΕΛΖΛγΓΖΛρΛΖΛΩΛξΓΔΛΒΛΤΛœΛόΛΩΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛΈΛΖΛψΛΌΛκΛ≥Λ»ΛρΙP”¦ΛΖΛΩΛξΛΙΛκΛΈΛάΛ§ΓΔν^Λ§ΛηΛΛΛΈΛ«¥σΛάΛΙΛΪΛξΛάΛ»ΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛœΓΔΛ»ΛΤΛβΛηΛμΛ≥ΛσΛ«ΛΛΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΠΛΖΛΤΟά“≤Ή”Λ§öΑ»’ΛΈΛηΛΠΛΥΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛΈΛ»Λ≥ΛμΛΊ≥ω»κΛξΛρΛΖΛΤΛΛΛκΛΠΛΝΛΥΓΔΝΦΤΫΛœΛ»ΛΤΛβΟά“≤Ή”Λ§ΛΙΛ≠ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΛΈΛάΓΘ
ΓΓΛΫΛ≥Λ«ΓΔΛΔΛκΛ»Λ≠ΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛΥΓΔ
ΓΗΛΆΛ®ΓΔΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΓΔΟά“≤Ή”ΛΒΛσΛΏΛΩΛΛΛ Λ“Λ»Λ§ΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛΈΛΣΛηΛαΛΒΛσΛΥΛ ΛκΛ»ΛΛΛΛΛΆΓΙ
ΓΓΛ»ΓΔΛΖΛΪΛΡΛαΛιΛΖΛΛνÜΛρΛΖΛΤΛΛΛΠΛ»ΓΔΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛœΛ”ΛΟΛ·ΛξΛΖΛΤΓΔΝΦΤΫΛΈνÜΛρ“äΛ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΛόΛΔΓΔΝΦΤΫΛΟΛΩΛιΓΔΛ ΛΥΛρΛΛΛΠΛΈΓΘΛΔΛ ΛΩΛœΛόΛά÷–―ßΛΈ“ΜΡξΛήΛΠΛΚΛΗΛψΛ ΛΛΛΈΓΘΛΫΛσΛ Λ≥Λ»ΩΦΛ®ΛκΛβΛσΛΗΛψΛΔΛξΛόΛΜΛσΛηΓΙ
ΓΗΛάΛΟΛΤΓΔΟά“≤Ή”ΛΒΛσΓΔΛ»ΛΤΛβΛΛΛΛΛ“Λ»ΛάΛβΛΈΓΘΛΫΛλΛΥν^ΛβΛΛΛΛΛΖΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛΈΛΣ ÷¹ΜΛΛΛάΛΟΛΤΛηΛ·Λ«Λ≠ΛκΛσΛάΛβΛΈΓΙ
ΓΗΛάΛαΓΔΛάΛαΓΔΉ”Λ…ΛβΛ§ΛΫΛσΛ Λ≥Λ»ΛΛΛΠΛβΛσΛΗΛψΛΔΛξΛόΛΜΛσΓΙ
ΓΓΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛœΛΫΛΠΛΛΛΟΛΤΓΔΝΦΤΫΛρΛΩΛΖΛ ΛαΛΩΛ§ΓΔΛΖΛΪΛΖΓΔΛΫΛΈνÜΛρ“äΛκΛ»ΓΔ…ΌΛΖΛβΛΣΛ≥ΛΟΛΤΛΛΛκΛηΛΠΛ«ΛœΛ Λ·ΛΤΓΔΛΪΛ®ΛΟΛΤΓΔΞΥΞ≥ΞΥΞ≥ΛΖΛΤΛΛΛκΛΈΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΟά“≤Ή”Λ§ΓΔ…Φ³Ό÷°÷ζΛ»ΛΛΛΠΛ“Λ»ΛΈΫΘΐΛρ“äΛΤΓΔΛ…ΛΠΛΖΛΤΛΔΛσΛ ΛΥΤϋΛ≠ΛάΛΖΛΩΛΈΛΪΓΔΟά“≤Ή”ΛœΉ‘öΔΛΖΛΩΛ»ΛΛΛΠΧλ≤≈Μ≠Φ“ΛΥΓΔΛ…ΛσΛ ΛΠΛιΛΏΛ§ΛΔΛκΛΈΛάΛμΛΠΛΪΓ≠Γ≠ΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΛ»Λ≠ΝΦΤΫΛΈν^ΛΥΞ’ΞΟΛ»ΛΠΛΪΛσΛάΛΈΛœΓΔΛ≠ΛγΛΠΙ≈ΒάΨΏΈίΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΔΛΔΛΈöίΈΕΛΈêôΛΛΡ–ΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛκΓΘΛΔΛΈΡ–ΛœΛ»ΛΤΛβΛΔΛΈΫΘΐΛρΛέΛΖΛ§ΛΟΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΛΔΛλΛΥΛœΛ ΛΥΛΪΓΔΛ’ΛΪΛΛΛοΛ±Λ§ΛΔΛκΛΈΛ«ΛœΛΔΛκΛόΛΛΛΪΓ≠Γ≠ΓΘ
ΓΓΛΫΛΠΩΦΛ®ΛκΛ»ΓΔΛΔΛΈöίΈΕΛΈêôΛΛêôΡßΛΈΜ≠œώΛΥΓΔΛ ΛΥΛΪΛ’ΛΪΛΛΟΊΟήΛ§ΛΔΛξΛΫΛΠΛΥΥΦΛ®ΛΤΓΔΝΦΤΫΛœ–ΊΛ§ΞοΞ·ΞοΞ·ΛΖΛΤΛ·ΛκΛΈΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΛΙΛΙΛξΤϋΛ·…υ
ΓΓΛΫΛΈΆμΛΈ’φ“Ι÷–Λ¥ΛμΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΝΦΤΫΛœΛΆΛ…Λ≥ΛΈΛ ΛΪΛ«ΓΔΛ’Λ»ΡΩΛρΛΒΛόΛΖΛΩΓΘΛ…Λ≥ΛΪΛ«Λ“Λ»ΛΈΛΙΛΙΛξΤϋΛ·ΛηΛΠΛ …υΛ§ΓΔ¬³Λ≥Λ®ΛΩΛηΛΠΛ öίΛ§ΛΖΛΩΛΪΛιΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΝΦΤΫΛœΞœΞΟΛ»ΛΖΛΤΓΔΛ·ΛιΛ§ΛξΛΈΛ ΛΪΛ«ΕζΛρΛΙΛόΛΖΛΩΓΘΛΙΛΙΛξΤϋΛ·…υΛœΛβΛΠ¬³Λ≥Λ®Λ ΛΪΛΟΛΩΛ§ΓΔιgΛβΛ Λ·ΓΔΞ§ΞΩΞξΛ»ΓΔΛ ΛΥΛΪΛΈΒΙΛλΛκΛηΛΠΛ “τΛ§ΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΝΦΤΫΛœΓΔΞœΞΟΛ»ΓΔΛΆΛ…Λ≥ΛΪΛιΛœΛΆΛΣΛ≠ΛΩΓΘ
ΓΓΛΛΛόΛΈΈο“τΛœΓΔΛΩΛΖΛΪΛΥèξΫ” “ΛΪΛ鬳Λ≥Λ®ΛΩΛΈΛάΓΘ
ΓΓΝΦΤΫΛΈΛΔΛΩΛόΛΥΓΔΛΫΛΈΛ»Λ≠ΓΔΞΒΞΟΛ»ΥΦΛΛΛΠΛΪΛσΛάΛΈΛœΓΔèξΫ” “ΛΥΛΔΛκêôΡßΛΈΜ≠œώΛΈΛ≥Λ»ΓΘΛΫΛλΛ»Ά§ïrΛΥΓΔΙ≈ΒάΨΏΈίΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΔΛΔΛΈöίΈΕΛΈêôΛΛΡ–ΛΈΡΩΛΡΛ≠ΛδΛ≥Λ»Λ–ΛρΥΦΛΛΛάΛΙΛ»ΓΔΝΦΤΫΛœΛ ΛσΛ»ΛβΛΛΛ®ΛΧΩ÷ΛμΛΖΛΒΛρΗ–ΛΗΛ ΛΛΛ«ΛœΛΛΛιΛλΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛ“ΛγΛΟΛ»ΛΙΛκΛ»ΓΔΛΔΛΈΡ–Λ§ΓΔêôΡßΛΈΜ≠œώΛρΛΧΛΙΛΏΛΥΛ≠ΛΩΛΈΛ«ΛœΛΔΛκΛόΛΛΛΪΓ≠Γ≠ΓΘ
ΓΓΝΦΤΫΛœ–ΡΡ†Λ§Ξ§ΞσΞ§ΞσΛΣΛ…ΛΟΛΤΓΔ»Ϊ…μΛΪΛιΛΡΛαΛΩΛΛΚΙΛ§ΛΥΛΗΛΏ≥ωΛκΛΈΛρΗ–ΛΗΛΩΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΝΦΤΫΛœΛΙΛΑΛΥΓΔΛΗΛ÷ΛσΛ§Λ≥ΛοΛ§ΛΟΛΤΛΛΛΤΛœΛΛΛ±Λ ΛΛΛΈΛάΛ»ΩΦΛ®ΛΩΓΘΛΝΛγΛΠΛ…ΛΫΛΈΛ≥ΛμΓΔΛΣΛ»ΛΠΛΒΛσΛœ Υ ¬ΛΈΛΩΛαΛΥΓΔ °»’ΛέΛ…ΛΈ”ηΕ®Λ«ΓΔιvΈςΛΈΛέΛΠΛΊ¬Ο––ΛΖΛΤΛΛΛκΛΒΛΛΛΝΛεΛΠΛάΛΟΛΩΛΈΛ«ΓΔΛΗΛ÷ΛσΛ§ΛΖΛΟΛΪΛξΛΖΛ Λ±ΛλΛ–ΛΛΛ±Λ ΛΛΛΈΛάΛ»¦Q–ΡΛΖΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΝΦΤΫΛœΛΫΛΟΛ»ΛΆΛ…Λ≥ΛΪΛιΛΧΛ±ΛάΛΙΛ»ΓΔκxΛλΛΥΛΆΛΤΛΛΛκΛΣΛΗΛΒΛσΛρΛΣΛ≥ΛΖΛΥΛΛΛΟΛΩΓΘ
ΓΗΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛΣΛ≠ΛΤΛ·ΛάΛΒΛΛΓΙ
ΓΓΛ·ΛιΛ§ΛξΛΈΛ ΛΪΛ«ΛΣΛΗΛΒΛσΛρΛφΛΙΛ÷ΛΟΛΤΛΛΛκΛ»ΓΔèξΫ” “ΛΈΛέΛΠΛΪΛιΛόΛΩΛΊΛσΛ …υΛ§¬³Λ≥Λ®ΛΤΛ≠ΛΩΓΘΛάΛλΛΪΛ§ΛΙΛΙΛξΤϋΛΛΛΤΛΛΛκΛΈΛάΓΘΛΫΛλΛρ¬³Λ·Λ»ΝΦΤΫΛœΓΔ»Ϊ…μΛΥΛΡΛαΛΩΛΛΥ°ΛρΛΪΛ±ΛιΛλΛΩΛηΛΠΛ ΓΔΩ÷ΛμΛΖΛΒΛ»öίΈΕêôΛΒΛΥΓΔΞ§ΞΩΞ§ΞΩΛ»Λ’ΛκΛ®Λ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛΣΛ≠ΛΤΛ·ΛάΛΒΛΛΓΙ
ΓΓΛφΛΙΛ÷ΛΟΛΤΛΛΛκΛ»ΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛœΛδΛΟΛ»ΡΩΛρΛΒΛόΛΖΛΩΓΘ
ΓΗΝΦΤΫΛΪΓΘΛ…ΛΠΛΖΛΩΛσΛάΓΘΛΛΛόΛ¥ΛμΓ≠Γ≠ΓΙ
ΓΗΛΣΛΗΛΒΛσΓΔèξΫ” “ΛΈΛ ΛΪΛΥΛάΛλΛΪΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΓΙ
ΓΗΛ…ΛμΛήΛΠΘΩΓΙ
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛœΛ”ΛΟΛ·ΛξΛΖΛΤΛœΛΆΛΣΛ≠ΛΩΓΘ
ΓΗΛ®Λ®ΓΔΛ«ΛβΓΔΛάΛλΛΪΤϋΛΛΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΓΙ
ΓΗΤϋΛΛΛΤΛΛΛκΘΩΓΙ
ΓΓΛ·ΛιΛ§ΛξΛΈΛ ΛΪΛ«ΓΔΛ’ΛΩΛξΛ§ΕζΛρΛΙΛόΛΖΛΤΛΛΛκΛ»ΓΔèξΫ” “ΛΈΛέΛΠΛ«ΓΔΛόΛΩΞ§ΞΩΞξΛ»Έο“τΛ§ΛΖΛΩΓΘΛΫΛλΛρ¬³Λ·Λ»ΛΣΛΗΛΒΛσΛœΓΔΛΆΛ…Λ≥ΛΪΛιΛ»Λ”ΛάΛΖΓΔΛ·ΛιΛ§ΛξΛΈΛ ΛΪΛ«éΓΛρΛΖΛαΛ ΛΣΛΖΛΤΓΔΛΊΛδΛΪΛι≥ωΛκΛ»ΓΔ
ΓΗΝΦΤΫΓΔΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛœΘΩΓΙ
ΓΗΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛœ÷ΣΛιΛ ΛΛΛηΛΠΛ«ΛΙΓΙ
ΓΗΛηΛΖΓΔΛΗΛψΓΔΛΫΛΈΛόΛόΛΥΛΖΛΤΛΣΛ±ΓΘΛ”ΛΟΛ·ΛξΛΒΛΙΛ»ΛΛΛ±Λ ΛΛΛΪΛιΓΘΝΦΤΫΓΔΛΣΛόΛ®ΛΗΛ÷ΛσΛΈΛΊΛδΛΊΛΛΛΟΛΤ“Α«ρΛΈΞ–ΞΟΞ»Λρ≥÷ΛΟΛΤΛ≥ΛΛΓΙ
ΓΓΝΦΤΫΛ§Ξ–ΞΟΞ»Λρ≥÷ΛΟΛΤΛ·ΛκΛ»ΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛœΓΔΛΫΛλΛρΤ§ ÷ΛΥΛ“ΛΟΛΒΛ≤ΛΤΓΔèξΫ” “ΛΈΞ…ΞΔΛΈΛόΛ®ΛόΛ«ΞΫΞΟΛ»ΛΖΛΈΛ”ΛηΛΟΛΩΓΘΝΦΤΫΛβΛΫΛΈΛΔΛ»ΛΪΛιΛ·ΛΟΛΡΛΛΛΤΛΛΛ·ΓΘ–ΡΡ†Λ§Ξ§ΞσΞ§ΞσΛΣΛ…ΛΟΛΤΓΔ–ΊΛ§ΛδΛ÷ΛλΛΫΛΠΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓèξΫ” “ΛΈΛ ΛΪΛΥΛœΛΩΛΖΛΪΛΥΛάΛλΛΪΛΛΛκΛΈΛάΓΘΞ§ΞΒΞ§ΞΒΛ»ΛΛΛΠ“τΛ§¬³Λ≥Λ®ΛκΓΘΛΖΛΪΛΖΓΔΛ’ΛΖΛ°Λ Λ≥Λ»ΛΥΛœΛΫΛλΛΥΛόΛΗΛΟΛΤΓΔΛ“Λ·ΛΛΛΙΛΙΛξΤϋΛ≠ΛΈ…υΛ§¬³Λ≥Λ®ΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛβΛΫΛλΛρ¬³Λ·Λ»ΓΔΛΒΛΙΛ§ΛΥΞ°ΞγΞΟΛ»ΛΖΛΤΓΔœΔΛρΛΈΛσΛάΛ§ΓΔΛΙΛΑΛΥöίΛρΛ»ΛξΛ ΛΣΛΖΛΤΓΔΞ…ΞΔΛΈΛΥΛ°ΛξΛΥ ÷ΛρΛΪΛ±ΛκΛ»ΓΔΛΛΛ≠Λ ΛξΛΑΛΟΛ»ΛύΛ≥ΛΠΛΊ―ΚΛΖΛ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΛάΛλΛάΘΓΓΓΛΫΛ≥ΛΥΛΛΛκΛΈΛœΘΓΓΙ
ΓΓΛΫΛΈΛ»ΛΩΛσΓΔΛΊΛδΛΈΛ ΛΪΛ«ΛœΓΔΞ…ΞΩΞ–ΞΩΛ»ΛΛΛΙΛδΞΤ©Γ°Ξ÷ΞκΛΥΛ÷ΛΡΛΪΛκ“τΛ§ΛΖΛΩΛ§ΓΔΛδΛ§ΛΤΛάΛλΛΪΛ§ΖôΛΪΛιΆβΛΊΛ»Λ”ΛάΛΖΛΩΓΘ
ΓΗΛΝΛ·ΛΖΛγΛΠΓΔΛΝΛ·ΛΖΛγΛΠΘΓΓΙ
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛœΛύΛΝΛψΛ·ΛΝΛψΛΥΞ…ΞΔΛρ―ΚΛΖΛΩΛ§ΓΔΛύΛ≥ΛΠΛΪΛιΓΔΛΡΛΟΛΪΛΛΛήΛΠΛ§ΛΖΛΤΛΔΛκΛιΛΖΛ·ΓΔ °ΞΜΞσΞΝΛέΛ…ΛΖΛΪΛ“ΛιΛΪΛ ΛΛΓΘ
ΓΗΛάΛαΛάΓΘΝΦΤΫΓΔΆΞΛΈΛέΛΠΛΪΛιΛόΛοΛμΛΠΓΙ
ΓΓΛΪΛΟΛΤΩΎΛΪΛιΆΞΛΊ≥ωΛκΛ»ΓΔ―YΡΨëθΛ§ΛΔΛ±ΛΟΛ―Λ ΛΖΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΛ’ΛΩΛξΛœΛΙΛΑΛΫΛ≥ΛΪΛιΒάΛΊΛ»Λ”ΛάΛΖΛΩΛ§ΓΔΛΔΛδΛΖΛΛΛβΛΈΛΈ”ΑΛœΓΔΛβΛΠΛ…Λ≥ΛΥΛβ“äΒ±ΛΩΛιΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΩΛ ΛΖΛΥΛ’ΛΩΛξΛœΓΔèξΫ” “ΛΈΖôΛΈœ¬ΛόΛ«Λ“Λ≠ΛΪΛ®ΛΖΛΤΛ≠ΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΛ»ΛΩΛσΓΔΞ°ΞγΞΟΛ»ΛΖΛΩΛηΛΠΛΥœΔΛρΛΈΛΏΛ≥ΛσΛάΓΘ
ΓΓΖôΛΈΛ ΛΪΛΪΛιΓΔΛόΛάΛΙΛΙΛξΤϋΛ≠ΛΈ…υΛ§¬³Λ≥Λ®ΛΤΛ·ΛκΛ«ΛœΛ ΛΛΛΪΓΘ
ΓΓΝΦΤΫΛβΛΣΛΗΛΒΛσΛβΓΔΛΫΛλΛρ¬³Λ·Λ»ΞΨΞΟΛ»ΛΖΛΩΛηΛΠΛΥνÜΛρ“äΚœΛοΛΜΛΩΛ§ΓΔΛΙΛΑΛΡΛ°ΛΈΛΖΛεΛσΛΪΛσΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΛœΖôΛρΛΈΛήΛΟΛΤΓΔΛΊΛδΛΈΛ ΛΪΛΊΛ»Λ”Λ≥ΛσΛάΓΘΝΦΤΫΛβΛΫΛλΛΥΛΡΛ≈ΛΛΛΩΛ≥Λ»ΛœΛΛΛΠΛόΛ«ΛβΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛ§κäöίΛΈΞΙΞΛΞΟΞΝΛρΛ“ΛΆΛΟΛΩΛΈΛ«ΓΔèξΫ” “ΛœΛΙΛΑΛΥΟςΛκΛ·Λ ΛΟΛΩΛ§ΓΔ“äΛκΛ»ΓΔΛΫΛ≥ΛΥΛœΛ“Λ»ΛξΛΈ…Ό≈°Λ§ΓΔΛΛΛΙΛΥΛΖΛ–ΛιΛλΓΔΛΒΛκΛΑΛΡΛοΛρΛœΛαΛιΛλΛΤΓΔΡΩΛΥΛΛΛΟΛ―ΛΛ¦φΛρΛΩΛΩΛ®ΓΔΛύΛΜΛ”ΤϋΛΛΛΤΛΛΛκΛ«ΛœΛ ΛΛΛΪΓΘ
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛœΛΛΛΫΛΛΛ«ΛΫΛΈΞ ΞοΛρΛ»Λ≠ΓΔΛΒΛκΛΑΛΡΛοΛρΛœΛΚΛΖΛΤΛδΛκΛ»ΓΔ
ΓΗΛ≠ΛΏΛœΛΛΛΟΛΩΛΛΛάΛλΛ ΛΈΓΘΛ…ΛΠΛΖΛΤΓΔΛΛΛόΛ¥ΛμΛ≥ΛσΛ Λ»Λ≥ΛμΛΊΛδΛΟΛΤΛ≠ΛΩΛΈΘΩΓΙ
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛœΓΔΛ«Λ≠ΛκΛάΛ±ΛδΛΒΛΖΛ·ΛΩΛΚΛΆΛΩΛ§ΓΔ…Ό≈°ΛœΛΩΛάΛβΛΠΤϋΛ·Λ–ΛΪΛξΛ«ΓΔΛ ΛΪΛ ΛΪΛ≥ΛΩΛ®ΛηΛΠΛ»ΛœΛΖΛ ΛΛΛΈΛάΓΘ
ΓΗΝΦΤΫΓΔΛΣΛόΛ®Λ≥ΛΈΉ”÷ΣΛΟΛΤΛκΘΩΓΙ
ΓΗΛΠΛΠΛσΓΔΛήΛ·ΓΔ÷ΣΛξΛόΛΜΛσΓΘΛΛΛόΛόΛ«“ΜΕ»Λβ“äΛΩΛ≥Λ»ΛΈΛ ΛΛΉ”Λ«ΛΙΓΙ
ΓΓΛόΛΟΛΩΛ·ΛΫΛλΛœ“ä÷ΣΛιΛΧ…Ό≈°ΛάΛΟΛΩΓΘΛ»ΛΖΛœΝΦΤΫΛ»ΛΣΛ ΛΛΛ…ΛΖΛ·ΛιΛΛΛάΛμΛΠΓΘΛΏΛ ΛξΛ≥ΛΫΛόΛΚΛΖΛΛΛ±ΛλΛ…ΓΔΛΪΛοΛΛΛΛΓΔΛξΛ≥ΛΠΛΫΛΠΛ νÜΛρΛΖΛΩ…Ό≈°ΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛœΛόΛΩΓΔΛ ΛΥΛΪΛΛΛΛΛΪΛ±ΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΛ»Λ≠Ξ…ΞΔΛρΆβΛΪΛιΛΩΛΩΛΛΛΤΓΔ
ΓΗΛόΛΔΓΔ–ά»ΐΛΒΛσΓΔΝΦΤΫΓΔΛ…ΛΠΛΖΛΩΛΈΓΘΛ ΛΥΛΪΛΔΛΟΛΩΛΈΓΘΛΛΛόΛΈΛΒΛοΛ°ΛœΛ…ΛΠΛΖΛΩΛΈΘΩΓΙ
ΓΓΛΫΛΠΛΛΛΠ…υΛœΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛ«ΛΔΛκΓΘ“äΛκΛ»Ξ…ΞΔΛΈΛΠΛΝΛ§ΛοΛΥΛœΓΔ¥σΛ≠Λ ιLΛΛΛΙΛ§―ΚΛΖΛΡΛ±ΛΤΛΔΛκΓΘΛΣΛΗΛΒΛσΛœΛΫΛλΛρ―ΚΛΖΛΈΛ±Λ Λ§ΛιΓΔ
ΓΗΞΔΞΟΞœΞΟΞœΓΔΛΆΛ®ΛΒΛσΓΔΛ ΛΥΛβΛ¥–Ρ≈δΛ ΛΒΛκΛ≥Λ»ΛœΛΔΛξΛόΛΜΛσΛηΓΘΛ…ΛμΛήΛΠΛ§ΛœΛΛΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΙΛ§ΛΆΓΔΛΪΛοΛΛΛΛΛΣΛ≠ΛΏΛδΛ≤ΛρΛΣΛΛΛΤΓΔΧ”Λ≤ΛΤΛΖΛόΛΛΛόΛΖΛΩΛηΓΙ
ΓΗΛόΛΔΓΔΛΫΛΖΛΤΛ ΛΥΛΪΛ»ΛιΛλΛΩΛΈΓΙ
ΓΓΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛΈΛΫΛΈΛ≥Λ»Λ–ΛΥΝΦΤΫΛœΓΔΛœΛΗΛαΛΤöίΛ§ΛΡΛΛΛΩΛηΛΠΛΥΓΔΛΊΛδΛΈΛ ΛΪΛρ“äΛόΛοΛΖΛΩΛ§ΓΔΛΙΛΑΞΔΞΟΛ»Ϋ–Λ÷Λ»ΓΔ
ΓΗΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛΣΛΗΛΒΛσΓΔΛδΛΟΛ―ΛξΛΫΛΠΛάΛηΓΘΛ…ΛμΛήΛΠΛœΛΔΛΈΫΘΐΛρΛΧΛΙΛΏΛΥΛ≠ΛΩΛσΛάΛηΓΙ
ΓΓΛΫΛΈ…υΛΥΛΣΛΪΛΔΛΒΛσΛβΛΣΛΗΛΒΛσΛβΓΔΞœΞΟΛ»±ΎΛΈΛέΛΠΛρΛ’ΛξΛύΛΛΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΛ»ΛΩΛσΓΔΛ’ΛΩΛξΛ»ΛβΛΣΛβΛοΛΚ¥σΛ≠Λ·ΡΩΛρ“äèàΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΔΛΔΓΔΛ…ΛμΛήΛΠΛœΛΔΛ≠ΛιΛΪΛΥΓΔêôΡßΛΈΜ≠œώΛρΛΧΛΙΛΏΛΥΛ≠ΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΛΔΛΈ¥σΛ≠Λ Λ§Λ·Λ÷ΛΝΛΪΛιΓΔΛœΛΚΛΙΛ≥Λ»Λ§Λ«Λ≠Λ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛ«ΓΔΛ’ΛΝΛΪΛι«–ΛξΛΧΛΛΛΤΛΛΛ≥ΛΠΛ»ΛΖΛΩΛΈΛάΛμΛΠΓΘΑκΖ÷ΛέΛ…«–ΛξΛΧΛΪΛλΛΩΞΪΞσΞ–ΞΙΛ§ΓΔΞάΞιΞξΛ»Λ§Λ·Λ÷ΛΝΛΪΛιΛ÷ΛιΛΒΛ§ΛΟΛΤΛΛΛκΛΈΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΛ…ΛμΛήΛΠΛΈΆϋΛλΈο
ΓΓΛΣΛΗΛΒΛσΛ§κä‘£ΛρΛΪΛ±ΛκΛ»ΓΔ